
24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
「お金の勉強をはじめたい」「金融リテラシーを高めたい」と考えたとき、何から手をつけるべきか迷う人は多いでしょう。
NISA・iDeCo・保険など、あらゆる情報は溢れていますが、学ぶ順番を間違えると遠回りになりやすく、注意しなければなりません。
本記事では、お金の知識を効率よく身につけるための「学習ロードマップ」を紹介します。
さらに、自身の大切な資産を守り、将来の不安を解消する最短ルートを分かりやすく解説するので、参考になれば幸いです。
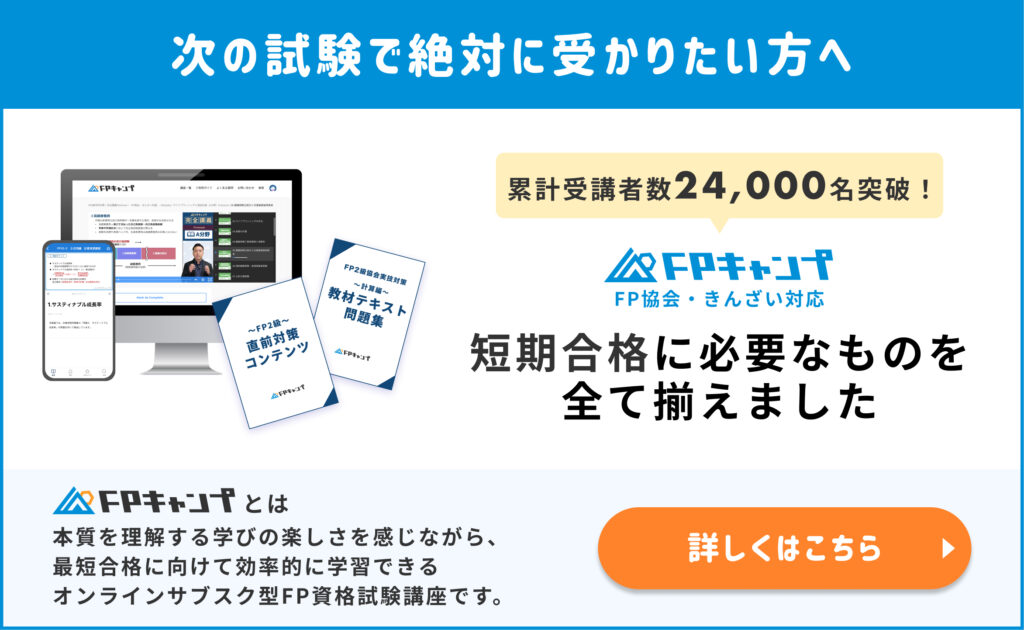
お金の知識は必要?学ぶべき3つの理由
「お金の知識」を学ぶべき3つの理由を紹介します。
①自分の資産を守り、増やせる
お金の知識を勉強すれば、自身の資産を「守り」、「増やす」スキルが身につきます。
お金の知識がない場合、手数料の高い金融商品の選択や、インフレによって資産が目減りするリスクに対応できません。
例えば、資産運用で得たリターン(利益)が非課税になる、NISA(少額投資非課税制度)が注目されています。
しかし、「みんなNISAしているし、私もやってみよう」と制度を活用するだけでは、投資で損失を生む可能性があるでしょう。
投資は、正しいお金の知識を活用しながら、リスク許容度を把握し、金融商品を選ばなければなりません。
リスク許容度とは、精神的・経済的に損失に耐えられる範囲を指し、リスク許容度に合った金融商品を選ぶ必要があります。
知識ゼロのままはじめてしまうと、耐えられない規模の損失につながり、生活に支障が出てしまうでしょう。
他にも、円安や物価高などの経済状況に対応し、資産価値の目減りを防ぐ「守り」の視点は、お金の知識が欠かせません。
知識は、自身の大切な資産を守る「盾」となり、かしこく増やす「武器」として役立ちます。
【リスク許容度の詳細はこちら】
▶リスク許容度とは?資産運用で失敗しないために知るべき目安と決め方
②お金に対する不安を安心に変えられる
お金の知識があれば、漠然とした「お金に対する不安」を、具体的な「安心」に変えられます。
多くの人が、お金に対する不安を感じているのではないでしょうか。
例えば、家計管理・老後資金・教育費・介護など、現在の経済状況から将来必要になるお金まで、あらゆる悩みは尽きません。
しかし、多くのお金の悩みは、「何に」「いつ」「いくら必要か」が分かっていない点が理由です。
一時期、「老後2,000万円問題」が話題になりましたが、これは2019年に発表された報告書にすぎません。
物価が上がり続ければ(インフレ)、2,000万円では足りなくなる可能性もあるでしょう。
また、本当に2,000万円が必要かは、個人の働き方・年金受給見込額・退職金の有無・ライフスタイルなどによって異なります。
お金の知識があれば、自身の条件や経済の変化から、本当に必要な金額を試算でき、より具体的な対策が可能です。
必要な金額とゴールが明確になれば、今から何をすべきかが分かり、行動計画を立てられます。
「今は2,000万円ないけれど、20年後には用意できる」と具体的に分かっていれば、将来の不安が安心へと変わります。
不安を「自身でコントロール可能な課題」へと変え、将来への安心感につなげられるのが「お金の知識」です。
③仕事につなげられる
お金の知識があれば、自身のキャリアや「仕事」につなげられます。
お金の知識や判断力を指す「金融リテラシー」は、特定の業界(金融・保険・不動産)以外でも活かせます。
例えば、教師をしている場合、生徒にお金の知識を教えられるため、生徒の未来を守れるでしょう。
リボ払いの恐ろしさや、若いからこそ複利運用を活かす大切さなど、さまざまな情報を提供できれば、実力を評価される可能性があります。
また、自身の働き方を見直すきっかけにもなるでしょう。
知識を活かして副業FPをはじめたり、独立系FPとして活動する道も開けます。
オンライン業務で無理のないセカンドキャリアをスタートできるなど、お金の知識があるだけで、選択肢は広がります。
FP資格を取得し、客観的にスキルを証明する必要がありますが、自身が歩みたい人生を叶えるきっかけになるでしょう。
【副業FP・独立系FP・セカンドキャリアの詳細はこちら】
▶独立系FPの仕事内容とは?メリットやデメリットなど徹底解説
【注意】断片的な勉強は、遠回りになりやすい
お金の問題はすべてが複雑に関連しているため、断片的な知識だけでは「本当の答え」を導き出せないためです。
お金の問題は、幅広い知識がないと対応できない
お金に関する悩みや課題の多くは、断片的な知識だけでは解決できません。
税金・保険・不動産・資産運用などの分野が、すべて関連しているため、幅広い知識が必要です。
例えば、家計を見直すとき、単純に「食費を削る」という節約術だけでは限界があります。
しかし、毎月のお金の流れを把握した上で、保険料を払いすぎている保険やサブスクの見直しをすれば、効率的に節約できます。
さらに、ふるさと納税や各所得控除を活用し、手元に残るお金を増やす工夫も可能になるでしょう。
全体像を理解してはじめて、自身の状況にとって何が優先の課題なのかが分かり、正しい対策を打てるようになります。
ケース①:資産運用
例えば、近年人気のある「資産運用」から勉強をはじめるケースを考えてみましょう。
多くの人が、リターンに税金がかからない「NISA」を活用しようと考えます。
しかし、家計の収支が赤字であったり、近い将来に使う予定のお金がある場合、慎重に検討すべきタイミングです。
流行りに任せてはじめたことが原因で、株価が下落したときに生活が立ちいかなくなり、損失を確定させる事態になりかねません。
そのため、自身のリスク許容度を把握し、生活防衛資金をしっかりと貯めてから、少額ずつ資産運用をはじめる方がよいでしょう。
生活防衛資金とは、病気・ケガ・失業などで収入が得られない期間を乗り越えるためのお金を指します。
働き方や家族構成などによって金額は異なりますが、生活費の3か月~6か月分を貯金するのが目安です。
市場の値動きに慣れたい人は、毎月1,000円から少額投資をはじめ、変化の耐性をつけながら生活防衛資金を貯めましょう。
世間の流れに身をゆだねず、安心して将来のために資産形成を進めるには、幅広いお金の知識が欠かせません。
ケース②:保険の見直し
「保険の見直し」をしたい人が、勉強するケースも考えてみましょう。
保険は万が一の事態に備える重要な仕組みですが、必要性は「国からの保障(公的保障)」を理解してはじめて判断できます。
例えば、日本には「高額療養費制度」があり、医療費の自己負担額には上限が定められています。
標準報酬月額28万〜50万円(区分ウ)の人が、100万円の治療を受けた場合、以下の金額で済みます。
8万100円 + ( 100万円 – 26万7,000円 ) × 1% = 8万7,430円
また、会社員や公務員が病気やケガで働けなくなった場合、「傷病手当金」から給与の約3分の2が最長1年6か月にわたり支給されます。
こうした公的保障の知識があれば、手厚すぎる保険に加入することなく、自身の資産をより豊かに活用できるでしょう。
断片的な知識だけで判断できないからこそ、経済的に余裕のある人生を過ごすためには、幅広いお金の知識は重要です。
お金の勉強はFP資格がおすすめ!全体像を把握できる
お金の知識を幅広く理解し、全体像をよりクリアにイメージするためには、「FP(ファイナンシャルプランナー)資格」がおすすめです。
これまで解説してきた通り、お金の勉強は「断片的な知識」ではなく「全体像」が軸になります。
しかし、書店に並ぶ本やYouTubeなどの動画を見るだけでは、各分野の関連性を理解できず、知識を活かせないでしょう。
FP資格の学習範囲は、人生に関わる以下の6分野をすべて学べます。
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
FPの勉強は、お金の専門家になるためだけのものではありません。
自身や家族の資産を守り、将来設計を立てるための「人生の教養」として、役立つ知識です。
効率よくお金の勉強を進めたい人こそ、「FP知識の学習からはじめる」のが、遠回りしない最短ルートだといえます。
【おすすめ】FP試験対策と同時進行したい!学習ロードマップ
FP試験対策と同時進行がおすすめの、「学習ロードマップ」を5つのステップで紹介します。
STEP1:現在地を知る(家計管理)
STEP1は、自身の「現在地」を正確に知る「家計管理」です。
収入がいくらあり、何にいくら使っているのか(支出)を把握しなければ、対策の立てようがありません。
まずは1か月から3か月程度、家計簿アプリなどを活用して収支を「見える化」することからはじめましょう。
クレジットカードや電子マネーと連携できる家計簿アプリもあるため、手書き家計簿で挫折経験がある人でも安心です。
このステップで、無駄な支出を発見し、見直すだけでも数千円から数万円の節約につながるでしょう。
STEP2:引かれるお金を知る(税金・社会保険)
STEP2は、給与から「引かれるお金」の「税金(所得税・住民税)」と「社会保険料(年金・健康保険料など)」を把握しましょう。
手取り額だけを見ていると、なぜその金額になるのかが分かりません。
しかし、どのような仕組みで税金や社会保険料が計算されているかを理解できれば、節税がなぜ有効なのか理解できます。
iDeCoやふるさと納税などを活用し、手元に残せるお金を増やしましょう。
STEP3:守りを固める(保険)
STEP3は、社会保険や民間保険について理解を深めましょう。
病気・ケガ・死亡などの事態が発生したときに、公的保障だけでは足りない部分(リスク)を特定します。
「足りない部分」だけを、民間の生命保険や医療保険で効率よく補うのが、かしこい保険の活用法です。
知識がないまま勧められた保険に入るのではなく、自身に必要な保障を判断するスキルを養いましょう。
必要以上に手厚い保障の保険に加入している場合は、保険の見直しを検討してみてください。
STEP4:将来の計画を立てる(ライフプラン・年金)
STEP4では、将来の目標や夢を実現させるために、具体的な計画(ライフプラン)を立てましょう。
例えば、結婚・出産・住宅購入・子供の教育・自身の老後などが挙げられます。
老後資金の課題をクリアしたい場合、公的年金がいつから、いくら貰えるのかを試算し、どれほどの金額を準備すべきか明確にしましょう。
具体的な計画があるからこそ、次のステップである資産運用の「ゴール」が決まります。
STEP5:お金を増やす(資産運用)
STEP5は、インフレからお金を守り、お金を増やす「資産運用」です。
STEP1〜4では、「いつまでに」「いくら必要か」「どれほどのリスクが取れるか」が明確になっています。
「何となく」はじめる投資とは違い、自身の条件に合わせた資産形成が進められるため、将来の安心を勝ち取りやすくなるでしょう。
市場の変化に動揺せず、冷静に着実に成功へと近づくためには、STEP1~5の流れが非常に重要です。
ロードマップを効率的に学ぶなら「FPキャンプ」が最適
「FP試験勉強、何からすればいいの?」と思う人におすすめなのが、ほんださんが運営するFP学習コンテンツ「FPキャンプ」です。
魅力①:実践で使える知識が身につく
FPキャンプでは、FP試験の合格のための、浅い知識は提供しません。
実生活に落とし込めるまで深く理解した、「実践的な知識」が身につきます。
制度ができた理由や背景、仕組みから丁寧に解説するため、応用力も養えるのがポイントです。
応用力がなければ、法改正があったり、自身の状況が変わったりしたときに対応できません。
FPキャンプでは、ほんださんの講義動画を通じて、税金や社会保険の「本質」を理解できます。
試験合格後も、自身の家計やライフプランに活かせる「一生モノの知識」を習得したい人は、ぜひFPキャンプではじめましょう。
魅力②:無料プランを提供
FPキャンプは、気軽に学習をはじめられる「無料プラン」を提供しています。
「いきなり有料プランは不安」「ほんださんの講義が自身に合うか試したい」という人にとって、学習のハードルが非常に低いでしょう。
無料プランでは、FP3級学科試験対策ができ、講義動画・オリジナル問題集などの学習コンテンツが使い放題です。
さらに、無期限で試せるため、仕事や家事で忙しい人でもじっくり挑戦できます。
無料プランでFPキャンプの分かりやすさを体感し、FP学習の第一歩を踏み出してみましょう。
【おすすめの記事】
【朗報】FP3級の独学が変わる!FPキャンプなら学科試験対策が無料で使い放題に
魅力③:有料プランは1か月約993円から
本格的な学習を目指す人には、コストパフォーマンスのよい「有料プラン」が用意されています。
例えば、FP3級(学科・実技試験対策)コースは、3か月間使い放題で2,980円(税込)です。
1か月あたり約993円という低価格で、合格に必要なコンテンツが利用できます。
スマホがあれば、いつでもどこでも、ほんださんの分かりやすい講義でインプット・アウトプット学習が可能です。
経済的な負担を抑えつつ、最短ルートで合格と実践的な知識の両方を手に入れたい人に向いています。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
お金の知識は、自分を守る盾となり、武器となる
お金の知識は、断片的な知識から入ると遠回りになりやすい傾向があります。
一方で、FP知識は税金・社会保険・保険・資産運用などの分野を網羅しており、各分野の関連性を理解できます。
幅広い知識があるからこそ、はじめて自身の状況に合わせた答えを導き出せ、夢や理想を実現させられます。
ぜひ、FP試験対策と同時並行で5つの学習ロードマップを進めてみてください。
得た知識をアウトプットできるため、より深く知識を身につけられるでしょう。
お金の知識は、これからの時代を生き抜く上で、自身と家族を守る「盾」であり、より豊かな人生を設計するための「武器」となります。
FPキャンプの学習コンテンツを活用しながら、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。









