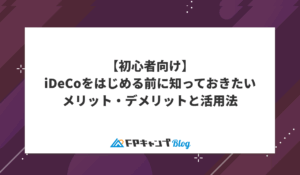24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、30万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年1月のFP1級試験では32%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
食料品や電気代など、さまざまなモノやサービスの値段が上がり、日々の生活に不安を感じている人も多いでしょう。
物価高から家計を守るためには、節約だけでなく、お金に対する正しい知識が必要です。
本記事では、物価高が起きる根本的な原因から、今日からはじめられる対策まで解説します。
さらに、物価高に対する不安を根本的に解消する「お金の知識」の学習についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
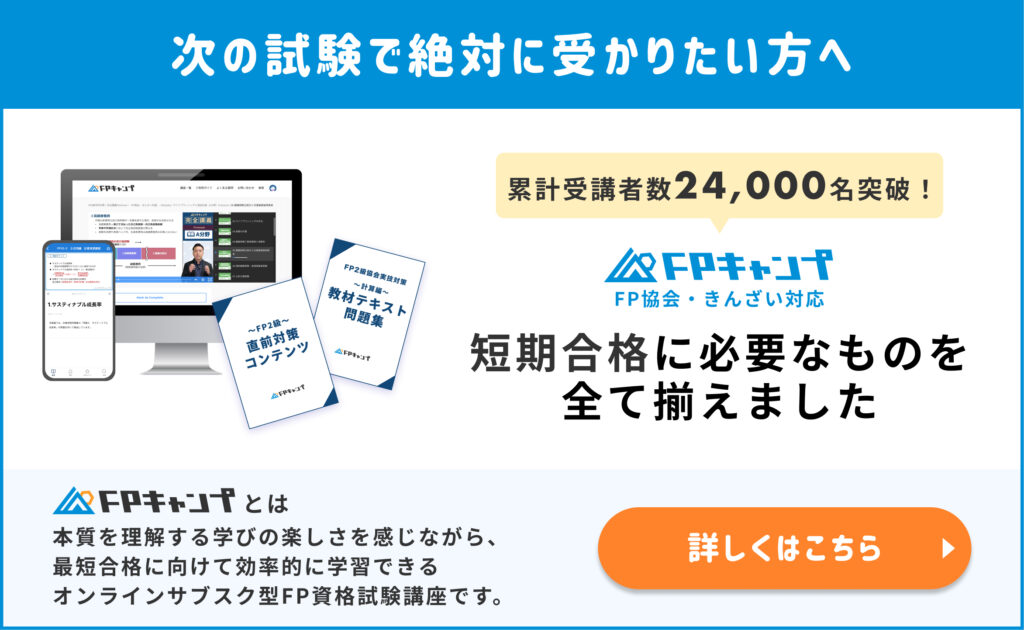
物価高と日本の現状とは?
現在、日本の物価は上がり続けており、この現象を「インフレ(インフレーション)」と呼びます。
スーパーでの買い物や毎月の光熱費の請求書を見るたびに、生活が圧迫されていると感じる人は少なくないでしょう。
日本の現状を示すデータとして、総務省が発表する「消費者物価指数」があります。
消費者物価指数とは、私たちが購入するモノやサービスの価格の変動を示し、物価が上がっているかどうかを確認できます。
例えば、お菓子の値段が同じでも、10個入りから8個入りに減った場合、お金の価値が下がっていることが分かるでしょう。
総務省では、消費者物価指数を毎月発表しており、2020年を基準とした2024年の平均値は以下の通りでした。
【2024年平均値】
- 総合指数:2020年を100として108.5
- 生鮮食品を除く総合指数:2020年を100として107.9
- 生鮮食品およびエネルギーを除く総合指数:2020年を100として107.0
参照:総務統計局「統計局ホームページ/消費者物価指数(CPI) 全国(最新の年平均結果の概要)」(2025年10月調査)
この結果を参考にすると、2020年に1,000円で買えたモノは、2024年では1,085円に値上がりしている計算が可能です。
※総合指数計算
さらに、2025年8月分の消費者物価指数を比較してみましょう。
【2025年8月分】
- 総合指数:2020年を100として112.1
- 生鮮食品を除く総合指数:2020年を100として111.6
- 生鮮食品およびエネルギーを除く総合指数:2020年を100として110.9
参照:総務省統計局「統計局ホームページ/消費者物価指数(CPI) 全国(最新の月次結果の概要)」(2025年10月調査)
2025年8月の結果によると、消費者物価指数が上がっており、2020年に1,000円で買えたモノが1,121円まで値上がりしています。
※総合指数計算
2024年の平均値と比較しても、1,000円の商品が36円値上がりしており、家計を圧迫する要因の1つです。
どうして物価高が起きているの?4つの原因を解説
物価高は、複数の複雑な要因が絡み合って発生しており、主な4つの原因を分かりやすく解説します。
①日本円の価値が下がる
物価高の原因の1つ目は、日本円の価値が下がる「円安」が挙げられます。
円安とは、海外の通貨(例:米ドル・ユーロ・ウォン)に対して、日本円の価値が下がっている状態です。
海外の通貨に対して円の価値が下がると、海外からモノを輸入する際に以前よりも多くの円を支払う必要が生じます。
例えば、10ドルの商品を輸入する場合、1ドル100円のときには1,000円で済みますが、1ドル150円になると1,500円を支払う必要があります。
円安による値上がりが、輸入製品・輸入品を原材料とする国内製品の価格に反映され、私たちの身の回りのモノの値段が上がります。
②モノやサービスの値上げ
海外からの輸入品だけでなく、国内で生産されるモノやサービスの価格も上昇している点も大きな原因です。
- 原材料価格
製品を作るために必要な金属や木材などの価格が世界的に上昇し、企業の生産コストを押し上げています。
- 人件費
労働人口の減少など、人材を確保するための賃金が上昇傾向にあり、サービス価格などに反映されています。
- 物流コスト
燃料費の高騰やドライバー不足により、製品を消費者の元へ届けるための輸送費用が増加しています。
これらの要因が重なり、コスト上昇分を製品価格に反映せざるを得ない状況が物価高につながっています。
③異常気象による値段への影響
世界各地で頻発する干ばつや洪水などの異常気象も、物価高と無関係ではありません。
例えば、海外の主要な穀物生産地が大規模な干ばつに見舞われると、小麦やトウモロコシの収穫量が激減します。
供給が減れば価格が高騰し、小麦やトウモロコシを原料とするパンや麺類、飼料などの値段が上がります。
また、国内でも猛暑や豪雨によって野菜の収穫量が不安定になり、特定の野菜の価格が一時的に急騰するケースも珍しくありません。
このように、異常気象は私たちの生活に影響を及ぼし、家計を圧迫する一因となっています。
④海外の紛争などによる世界情勢の不安
特定の地域で発生する紛争や対立などの国際情勢の不安定さも、世界の経済に大きな影響を及ぼし、物価高の引き金の1つです。
例えば、エネルギー大国が含まれる地域で紛争が起きると、原油や天然ガスの価格が世界的に高騰します。
日本はエネルギーの多くを輸入に頼っているため、ガソリン代や電気・ガス料金の値上がりという形で、私たちの生活に打撃を与えます。
遠い国の出来事が、巡り巡って日本の物価を押し上げている要因です。
物価高対策におすすめな6つの方法
物価高から家計を守り、資産をかしこく育てるための、今すぐはじめられる6つの対策を紹介します。
①家計改善
物価高対策の基本は、自身の支出をしっかりと把握し、無駄をなくす「家計改善」です。
「今月の食費は〇万円くらいだろう」と考えていても、予想以上の出費につながっているケースもあり、数字として可視化させましょう。
何にいくら使っているかを把握できれば、「どの費用が無駄なのか」を明確にでき、お金の流れを確認できます。
例えば、節約を意識している人でも食費が高い場合、自販機で飲み物を購入したり、コンビニスイーツを頻繁に楽しんでいる可能性があります。
「節約しているのにお金が貯まらない」と感じる人は、このような原因が隠れているため、しっかりと確認しましょう。
他にも、必要以上の保障が受けられる高額な保険や、スマホやサブクスの料金など、さまざまな要因が挙げられます。
毎月のお金の流れを数字として把握し、毎月の固定費や変動費を見直せば、少しの工夫で大きな金額を節約できるでしょう。
②ポイ活
日々の買い物やサービスの利用でポイントを貯め、ポイントを支払いや投資に回す「ポイ活」も、手軽にはじめられる物価高対策です。
クレジットカードやスマホ決済サービスは、利用額に応じてポイントが還元されるものが多くあります。
例えば、楽天・PayPay・ドコモなど、支払いを特定のサービスに集約すれば、効率よくポイントが貯まるでしょう。
貯まったポイントで日用品を購入したり、光熱費の支払いに充てたりすれば、現金支出を減らし、家計の負担を軽減できます。
ただし、ポイ活に力を入れるよりも、後述の「④収入源を増やす」に時間を充てる方が大きな金額につながりやすい傾向にあります。
副業をしながら利用するサービス経済圏を絞るなど、効率的に物価高対策を進めてみましょう。
③資産運用
物価高対策となり、かつ物価高の恩恵を受ける方法は「資産運用」です。
物価が上がっていけば、現金の価値が目減りしていきます。
例えば、100円で購入できたお菓子が150円出さないと購入できない場合、以前よりも多くのお金を払わなければなりません。
一般的に、物価は上昇していくと考えられているため、対策をしなければ現金の価値は減り続けていくでしょう。
そのため、銀行預金にただお金を預けておくだけでは、インフレに負けて資産が実質的に減少してしまう恐れがあります。
NISA(少額投資非課税制度)などを活用し、投資信託などで長期・積立・分散投資をはじめるのがおすすめです。
資産運用にはリスクが伴いますが、世界経済の成長の恩恵を受けられ、インフレ率を上回るリターンを期待できます。
資産を守り、かしこく増やすための手段として資産運用は非常に有効です。
【おすすめの記事】
【最新】お金を増やし守る投資とは?FP資格があれば投資に有利って本当?
④外貨を持つ
物価高の原因の1つである「円安」への対策として、資産の一部を「外貨」で持つのもおすすめです。
日本円だけでなく、米ドルやユーロといった他の国の通貨を保有すれば、円の価値が下がったときのリスクを分散できます。
外貨預金やFX(外国為替証拠金取引)などで実践できるため、取り入れてみるとよいでしょう。
ただし、為替レートは常に変動しており、為替差損が生じるリスクもあるため、仕組みをよく理解した上ではじめる必要があります。
⑤収入源を増やす
支出を減らす「守り」の対策だけでなく、収入を増やす「攻め」の対策もインフレ対策に向いています。
現在の日本は、物価高が先行している「悪いインフレ」のため、給料に変化がなく、家計が圧迫されている状態です。
会社の業績や経済状況の変化によって影響を受け、業績悪化が原因による減給やボーナスカットされる可能性もあります。
そのため、現在の仕事で専門性を高めてキャリアアップを目指すだけでなく、空いた時間で副業をはじめるのも有効な手段です。
自身のスキルを活かせる仕事や、未経験からはじめられる仕事など、副業をはじめればより安定的な生活を過ごせるでしょう。
また、将来のキャリアを見据えて専門的なスキルや資格を習得し、より条件のよい企業への転職を目指すのもよい選択です。
収入源を複数持っていれば、万が一のときに冷静に対応できるだけでなく、本当に望む環境で働くチャンスにもつながります。
⑥お金の知識を学ぶ
ここまで紹介した5つの対策(家計改善・ポイ活・資産運用・外貨・収入増)をより活かすためには、正しいお金の知識が必須です。
どの保険が自身に適しているか、どの金融商品を選ぶべきかなどは、お金の知識があれば判断できるようになります。
保険会社や銀行で紹介される商品は、企業の方針や利益につながる商品を紹介している可能性が否定できません。
しかし、判断軸になるお金の知識があれば、「この保険は自分に必要ないな」「この投資信託は手数料が高い」などを判断できます。
物価高という厳しい状況だからこそ、お金に関する知識を身につけ、自身にとって最適な選択をできる基盤が重要です。
1番の物価高対策!お金の知識なら「FP資格」が最適
お金の知識を学びたい人におすすめの「FP資格」について解説します。
理由①:お金について幅広く把握できる
FP資格の正式名称は「ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)」といい、3級・2級・1級のレベルに分かれた国家資格です。
FP技能士以外にも、民間資格のAFP、民間資格で国際ライセンスのCFPがあります。
FPの試験範囲は幅広く、以下の6分野の知識を学びます。
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
これらの知識は関連し合っており、幅広い知識を身につけることで、家計や資産の全体を考えた上で判断を下す力が養われます。
理由②:世界・日本の経済を理解できる
FPの学習内容は、経済に関わる専門用語や制度などのあらゆる知識を学ぶため、世界のお金の流れを把握できるようになります。
例えば、金融資産運用の分野では、金利や為替、物価の変動などの知識を学べるため、「今は円安だ」と現状を理解できます。
これまで「よく分からない」と感じていた経済ニュースを把握できるようになれば、世の中の動きを予測し、先回りした対策も可能です。
理由③:お金の悩みを根本的に解決可能
幅広いお金の知識があれば、物価高対策だけでなく、教育資金や老後資金の準備、マイホームか賃貸問題など、さまざまな問題を解決できます。
お金の知識があるからこそ、SNSの言葉をうのみにせず、正しい判断を下せるでしょう。
自身のライフプランを見据えた上で、長期的な視点で計画的に資産形成ができれば、より安心した日々を過ごせます。
お金に対する漠然とした不安が希望に変われば、経済状況が変化しても揺らがない、安定した家計の土台を築けます。
理由④:収入源を増やす力になる
FPの知識は、家計を「守る」だけでなく、収入を「増やす」力にもつながります。
金融機関や不動産業界への就職・転職に有利になるだけでなく、一般企業においても財務や経理部門で専門性を発揮できるでしょう。
また、FPの知識を活かして金融記事を執筆したり、個別のマネー相談を受けたりするなど、副業につなげる道も開けます。
FPの学習は、自身の市場価値を高め、収入増を実現するための自己投資ともいえます。
【注意】暗記に頼る知識は、実生活で活かしにくい
FP学習は、物価高をはじめとする多くの経済変化に対応できる重要な知識ですが、暗記だけの知識はおすすめできません。
税制や社会保険制度は、毎年のように改正されており、古い数値を暗記しているだけでは、実生活で当てはめにくい傾向にあります。
「なぜそのような制度なのか」といった制度の背景や本質を理解していなければ、予期せぬ事態や複雑なケースに対応するのは困難です。
本当の意味で物価高対策に活かすためには、単なる知識の丸暗記ではなく、変化に対応できる「生きた知識」を身につける必要があります。
実生活で活かせる生きた知識は、「FPキャンプ」で学ぼう
「暗記ではなく、本質を理解する学習がしたい」と考える人に最適なのが、ほんださんが運営するFP学習コンテンツ「FPキャンプ」です。
魅力①:「なぜ?」に先回りした本質授業
FPキャンプでは、受講者が抱く「なぜ?」に先回りした、本質を突く授業を提供しています。
制度の背景まで掘り下げて解説するため、単なる暗記ではなく、深い理解を伴った知識が定着します。
YouTubeでの分かりやすい解説で人気のほんださんだからこそ提供できる、納得感のある講義が特徴です。
この「なぜ?」を理解する学習スタイルこそが、変化の激しい時代に対応できる応用力を養います。
本当に使える知識を学びたい人こそ、FPキャンプとの相性はよいでしょう。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
魅力②:無料・無期限・使い放題からスタートできる
FPキャンプは、FP3級(学科試験対策)コースを無料で提供しています。
更新すれば無期限で利用でき、各学習コンテンツが使い放題のため、自分のペースで学習を進められます。
「FPの勉強がどんなものか試してみたい」「自分に合うか不安」という人でも、費用を気にすることなく気軽にスタートできるでしょう。
仕事や家事で忙しい人だけでなく、経済的に負担がネックで勉強をはじめられなかった人でも、無理なく続けられます。
【おすすめの記事】
【朗報】FP3級の独学が変わる!FPキャンプなら学科試験対策が無料で使い放題に
魅力③:有料プランは約1か月993円から!低価格で学習可能
より本格的な勉強をはじめ、FP3級・2級・1級とステップアップを目指す場合でも、FPキャンプは嬉しい低価格で学習をサポートします。
FP3級の学科・実技試験対策ができる有料コースは、3か月間使い放題で2,980円(税込)です。
1か月に換算すると約993円になり、経済的負担を軽くしながらより深く勉強ができます。
物価高で家計が厳しい状況だからこそ、自己投資の費用を抑えながら、本当の知識を得られるFPキャンプでスタートしてみませんか。
物価高対策をするには、正しい知識が重要!判断軸を確立しよう
物価高を乗り切るためには、目先の節約術に一喜一憂するのではなく、自身の中にゆるぎない「判断軸」を作る必要があります。
判断軸の土台となるのが、FPの学習を通じて得られる、本質的なお金の知識です。
お金の知識は一度身につければ、一生涯あなたを助けてくれる資産となります。
FPキャンプで「生きた知識」を学び、変化の激しい時代をかしこく生き抜く力を手に入れましょう。
あわせて読みたい!FP資格の関連記事はこちら
FP資格の詳細から実施団体、働き方まで紹介しています。
【実施団体】
【FPとして働く】