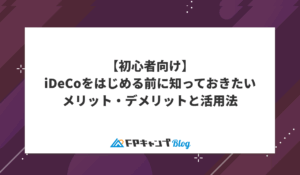24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、30万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年1月のFP1級試験では32%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
「将来のためにお金を貯めなければ」と思ってはいるものの、給料日前にはいつもお財布が寂しい状態の人も多いでしょう。
周りの人はしっかり貯金しているように見え、焦りや不安を感じるかもしれません。
しかし、貯金ができない理由は、お金が貯まる正しい仕組みや知識を知らないだけの可能性があります。
本記事では、FPの視点から、多くの人が陥りがちな貯金できない原因を解き明かします。
さらに、今日からはじめられる改善ステップや、無理なく続けられる手抜きテクまで詳しく解説するので、ぜひご覧ください。
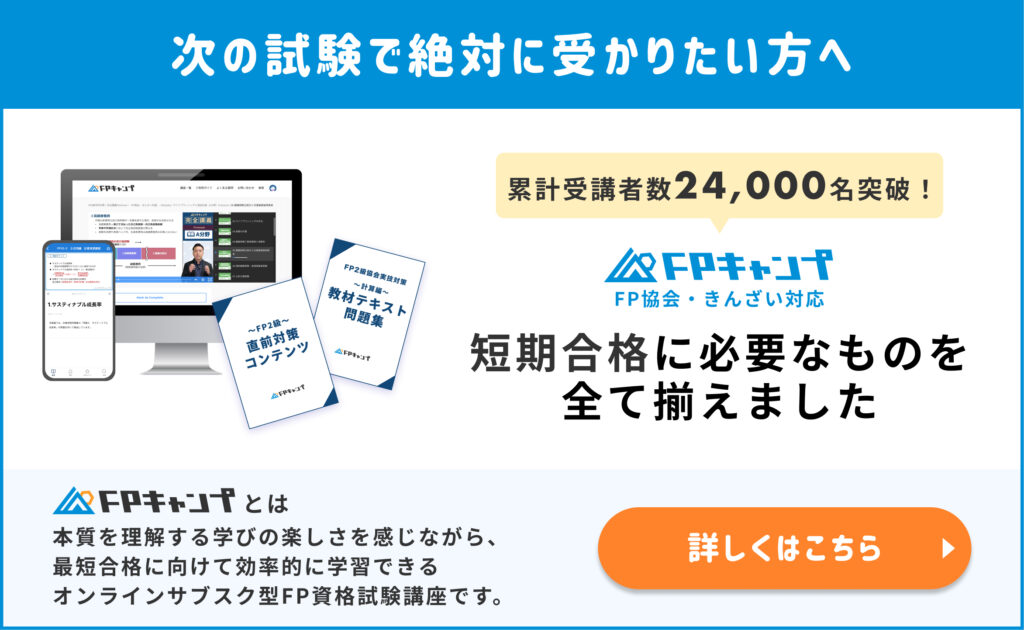
みんな貯金している?平均額を公開
「自分は全然貯金がないけれど、周りの人はどうなのだろう」と、他人の貯蓄事情が気になる人は多いかもしれません。
20代~70代の貯金額の平均値は、以下の通りです。
| 年代 | 預貯金(平均値) | 預貯金がない人の割合 |
|---|---|---|
| 20代 | 105万円 | 36.8% |
| 30代 | 286万円 | 28.4% |
| 40代 | 361万円 | 26.8% |
| 50代 | 472万円 | 27.4% |
| 60代 | 885万円 | 21.0% |
| 70代 | 774万円 | 19.2% |
このデータから見ても、貯金ゼロの状態の世帯は一定数おり、貯金ができないのは珍しいことではありません。
自身の状態を客観的に確認し、未来が待ちどおしくなるような資産形成をはじめていきましょう。
何個当てはまる?貯金できない人に共通する6つの原因
貯金ができない背景に隠れた原因を6つ紹介するので、自身がいくつ当てはまるかチェックしてみてください。
①お金の流れを把握できていない
貯金ができない根本的な原因は、自身のお金の流れ(収入と支出)を正確に把握できていない点が挙げられます。
例えば、「毎月の外食費は、2万円程度に収まっているだろう」と考えていたとします。
しかし、休日に何度も食事会などに参加していれば、倍以上の金額になっている可能性があるでしょう。
毎月何にいくら使っているか分からない曖昧な状態では、どこを節約すればよいのか判断できません。
家計簿をつけて自身の支出を記録し、お金の流れを「見える化」させ、抑えるべき費用をあぶりだしてみてください。
②貯金の目的や目標額が不明確
貯金をする目的や目標額を設定すれば、より具体的な計画を練れるだけでなく、モチベーションを維持できます。
ただ漠然と「お金を貯めたい」と思っているだけでは、日々の誘惑に勝てず、ついお金を使ってしまうでしょう。
貯金を成功させるには、「いつまでに」「何のために」「いくら貯めるか」という具体的な目標設定が必要です。
「1年後に沖縄旅行へ行くために20万円」「10年後までに教育資金として300万円」など、目標を決めてみてください。
目標が具体的でワクワクするものであればあるほど、貯金のモチベーションは高まります。
目的意識を持つことで、日々の節約も「我慢」ではなく「目標達成のためのプロセス」と前向きに捉えられるようになります。
③余った分だけ貯金している
「毎月の給料から生活費を払い、余った分を貯金しよう」という考え方は、貯金ができない人に多いパターンです。
先取り貯金をしない場合、収入分のお金を使い切ってしまう人が多くいます。
これは「パーキンソンの法則」としても知られており、支出は収入の額まで膨張するといわれています。
つまり、「余ったら貯金」では、いつまで経ってもお金は余らず、資産形成を進めることは難しいでしょう。
「給料が入ったら、まず貯金する分を確保し、残ったお金で生活する」という考え方に切り替え、コツコツと貯金するのがポイントです。
④コンビニや自販機での買い物が多い
つい油断してしまいがちですが、日常的な「ついで買い」は家計を圧迫する大きな要因です。
例えば、出勤前のコンビニコーヒーや、仕事帰りのご褒美スイーツ、自販機で買う飲み物などが当てはまります。
これらは「ラテマネー」とも呼ばれ、1回の会計額が数百円と小さな金額でも、毎日続ければ1か月で数千円以上の大きな金額になります。
こうした無意識の支出にメスを入れない限り、いくら大きな節約を試みても、貯金額はなかなか増えないでしょう。
小さな浪費の積み重ねを見直し、毎月の貯金額を増やしていくのがポイントです。
⑤固定費(スマホ代・保険など)が高い
家計の支出は、毎月金額が変動する「変動費」と、毎月ほぼ一定額が出ていく「固定費」に分けられます。
特に、固定費を見直せば、大きな金額の節約にもつながるため、ひとつずつ確認してみましょう。
例えば、家賃・通信費・保険料・サブスクリプションサービスなど、さまざまな料金が当てはまります。
これらは一度見直せば、その後は意識しなくても節約効果がずっと続くため、非常に効率がよいでしょう。
例えば、スマホを大手キャリアから格安SIMに変え、毎月約3,000円の節約につながったとします。
年間で計算すると約3.6万円、5年間で計算すると約18万円と、日々の細かな節約を積み重ねるよりも効率的です。
変動費を切り詰める前に、まずは固定費を見直してみましょう。
⑥貯金にまわすお金がない
「収入が少ないから、貯金に回すお金なんてない」と諦めている人も多いでしょう。
収入の金額も貯金に関係しますが、貯金ができない原因は先ほど紹介した①~⑤の理由が隠れているケースが多くあります。
実際に収入が少ない場合でもコツコツと貯金できている人もいるため、ひとつひとつ解決してみてください。
お金の流れをコントロールできれば、少額でも貯金に回せるお金を生み出せ、目標へと一歩ずつ近づけます。
貯金ができる人に変わる!FPが教える4ステップ
誰でも実践できる、貯金ができる人に変わるための4つのステップを紹介します。
ステップ①:現状の家計を把握する
まずは、自身の家計の現状を正確に把握しましょう。
最低でも1か月、できれば2〜3か月分の収入と支出を記録し、「何に」「いくら」使っているのかを明らかにします。
家計簿やExcelなどを活用し、コツコツとデータを集めていくのがポイントです。
ステップ②:目標を設定する
家計の現状が見えたら、次に貯金の目標を設定しましょう。
目標を立てるときに、以下の項目を具体的にするのがポイントです。
- 何に
- いくら
- いつまでに達成するか
(例)
- 何に:車を購入するため
- いくら:200万円
- いつまでに達成するか:2年後
上記のケースでは、200万円を2年で貯めるには、毎月約8.3万円貯金しなければなりません。
約8.3万円の貯金が難しいと感じれば、期間を延ばしたり、ボーナス時に多く入れたりするなど、より現実的な計画が可能です。
明確な目標を設定できれば、貯金を継続するためのモチベーションにもつながり、目標を達成しやすくなるでしょう。
ステップ③:先取り貯金を仕組み化する
目標金額を達成しやすい方法の1つ、先取り貯金を仕組み化するのがおすすめです。
先取り貯金とは、給料が振り込まれたら、使う前に貯金額を別の口座へ移してしまう方法を指します。
前述通り、「余ったら貯金しよう」ではなかなかお金は貯まらないため、意志の力に頼らない「仕組み」を作りましょう。
ステップ④:固定費と変動費を見直す
貯金額をさらに増やすためには、支出の見直しをするのがよいでしょう。
「固定費」に払いすぎている保険料やサブスク代はないか確認し、次に「変動費」の見直しをするのがおすすめです。
具体的には、スマホの料金プランの見直し、電力・ガス会社の切り替え、不要なサブスクリプションの解約、保険内容の確認などが挙げられます。
固定費の削減で余裕が生まれたら、次に食費や交際費といった変動費に目を向けます。
ただし、変動費の過度な切り詰めはストレスにつながるため、無理のない範囲で、メリハリをつけて見直すことが継続のコツです。
どうしても貯金ができない人におすすめの手抜きテク
面倒なことが苦手な人でも無理なく続けられる、究極の「手抜きテク」を紹介します。
①家計簿はアプリやAIで楽々管理
手書きの家計簿が続かなかった経験がある人は、最新のテクノロジーを頼りましょう。
例えば、家計簿アプリやAIを使った管理方法は、継続が苦手な人でも続けられるほど簡単です。
最近の家計簿アプリは高機能で、銀行口座やクレジットカード、電子マネーなどを登録しておけば、利用履歴を自動で取得します。
自身で入力する手間がほとんどないため、挫折する可能性が減り、現在の保有資産額も簡単に把握できるでしょう。
他にも、AIに使った金額を伝え、計算してもらう方法もおすすめです。
集計結果をエクセルやGoogleスプレッドシート形式で作成してもらえるため、見やすい方法でデータを管理できます。
面倒な作業はアプリやAIに任せて、楽々と家計管理を続けましょう。
②支払いはすべてキャッシュレスにして支出を見える化
家計管理を簡単にする方法の2つ目は、支払いを可能な限りキャッシュレスに統一することです。
現金払いをやめて、特定のクレジットカードやスマホ決済に集約するだけで、利用明細がそのまま家計簿代わりになります。
「今月は何にいくら使ったか」を把握したいとき、アプリの利用履歴を確認するだけで済みます。
また、管理の手間が省けるだけでなく、ポイント還元といった恩恵も受けられ、一石二鳥でしょう。
支出の流れがデータとして自動的に記録されるため、手軽に家計を見える化できる効果的な手段といえます。
家計簿アプリと組み合わせれば、楽々とカテゴリ別の家計管理を続けられるので、自分に合った方法を見つけてみてください。
③先取り貯金を自動化する
銀行が提供している「自動入金サービス」や「定額自動送金サービス」を活用すれば、先取り貯金を完全に自動化できます。
例えば、「毎月25日の給料日に、A銀行(給与振込口座)からB銀行(貯蓄専用口座)へ3万円を自動で送金する」という設定をするだけです。
あとは何もしなくても、毎月自動的にお金が貯蓄専用口座に移動し続けるため、ストレスが減るでしょう。
ただし、銀行によっては手数料がかかる可能性があるため、「〇回まで振込無料」といった条件のある銀行を選ぶのもおすすめです。
④デビットカードで使いすぎ防止
クレジットカードを使いすぎてしまう人におすすめなのが、デビットカードの活用です。
デビットカードは、支払いと同時に自身の銀行口座から代金が引き落とされる仕組みのため、口座残高以上にお金を使いすぎる心配がありません。
お金の管理が苦手で、支出をしっかりコントロールしたい人にとって、心強い味方になるでしょう。
根本解決を目指すなら「お金の知識」を学ぶのが最短ルート
本当の意味で「お金に困らない人生」を送るためには、幅広いお金の知識を学ぶのが近道です。
理由①:貯金の失敗パターンを根本から断ち切れる
家計簿が続かない人や無駄遣いをしてしまう人の背景には、お金に関する知識不足が隠れているケースがあります。
例えば、公的保障について理解していなければ、本当に必要な保険を見極められず、過度な保障内容の保険に加入する可能性も否定できません。
毎月数万円の保険料を支払っていては、貯金に回すお金を確保できず、目標金額を達成できないでしょう。
お金の知識を学べば、本当に必要な保険や最適な投資法を選べ、効率的にお金を増やし続けられます。
目先の問題を解決するテクニックに頼るのではなく、自身の状況に合った方法を自分で考え、失敗のパターンを根本から断ち切れます。
理由②:状況の変化に自分で対応し、資産を守れるようになる
経済状況や社会制度は常に変化しており、柔軟さが重要です。
例えば、インフレによる物価上昇・増税・年金制度の改正など、さまざまな変化が挙げられ、臨機応変に対応しなければなりません。
自身の資産を守るためには、断片的な節約術やテクニックだけでなく、幅広い知識から判断できるスキルが重要です。
知識は、自身の資産を守り、かしこく対応していくための「一生モノの武器」となるでしょう。
理由③:貯金以外の「お金の不安」もまとめて解消できる
貯金ができない悩みだけでなく、保険の選び方や老後資金準備など、複数のお金の課題を抱えている人も多いでしょう。
しかし、お金の知識があれば、これらの課題をまとめて解決できます。
保険・年金・税金・不動産などの人生全体に関わるお金の知識を身につけることで、将来を見越した計画が立てられます。
「老後のために30年かけて2,000万円貯金したい」と考えている場合、1年で約67万円貯金しなければなりません。
1か月で換算すると、月々約5.5万円貯金しなければならず、ハードに感じる人も多いでしょう。
一方、お金の知識があれば、リターンが非課税になるNISAを活用して資産運用する選択肢が増えます。
利回り3%の金融商品で30年間運用すれば、月々約3.4万円の投資額で済むため、目標達成がより現実的になります。
月々5.5万円投資できる場合は、約3,200万円準備できる計算になり、差額は1,200万円です。
知識があるからこそ、リスクを軽減させながら資産形成を進められ、より経済的自由な環境を作り上げられます。
お金の知識を体系的に学ぶなら、FP資格の勉強が最適
断片的な知識だけでなく、幅広いお金の知識を効率よく身につけたいなら、FP資格の学習がおすすめです。
FP資格の学習では、実生活に必要な6分野を学べ、各知識との関連性を意識した知識が身につきます。
また、「資格取得」という明確なゴールがあるため、学習のモチベーションを維持しやすい点も大きなメリットといえるでしょう。
無料ではじめられる!FP資格を学ぶなら、生きた知識を学べるFPキャンプ
これからお金の知識の学習をはじめたい人には、無料からはじめられるFPキャンプがおすすめです。
魅力①:実生活で役立つ生きた知識を学べる
FPキャンプの魅力は、単なる試験合格のための詰め込み学習ではなく、実生活で本当に役立つ「生きた知識」が身につく点です。
運営者であるほんださんは、YouTubeチャンネルでも高い人気を誇り、難しい金融のテーマを身近な例えを交えながら解説します。
FPキャンプでは、YouTubeよりもパワーアップした内容を提供しており、疑問に先回りした知識の本質を説明しています。
学んだ知識をすぐに自身の家計改善や資産形成に活かせるため、学習のモチベーションを高く維持できるでしょう。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
魅力②:無料から学習できるお得なプラン設定
「貯金がないから、勉強にお金をかける余裕がない」という人でも、FPキャンプなら安心して学習をはじめられます。
FPキャンプでは、誰でも気軽に学びに挑戦できるよう、無料から利用できるコンテンツが用意されています。
FP3級対策(学科試験)ができるコースは無料で提供しており、「まずは試してみたい」という人にもおすすめです。
さらに本格的に学びたいと感じたら、コストパフォーマンス抜群の有料プランを検討してみましょう。
FP3級(学科・実技試験)対策ができる有料コースは、3か月間使い放題で2,980円(税込)とリーズナブルな価格です。
1か月に換算すると約993円になり、経済的負担が気になる人でも安心して学べます。
学びたいと思ったその瞬間にスタートさせられるFPキャンプで、新しい環境を手に入れましょう。
【おすすめの記事】
【朗報】FP3級の独学が変わる!FPキャンプなら学科試験対策が無料で使い放題に
貯金できる環境はちょっとした工夫から!貯金ゼロを卒業しよう
貯金ができない理由には、複数の原因が隠されています。
正しいやり方を理解した上で無理なく継続できる仕組みを作ることで、貯金ゼロから卒業できます。
まずはお金の流れを把握し、先取り貯金を自動化して、着実に未来を変えていきましょう。
また、テクニックだけでなく、一生役立つお金の知識を身につけたいと感じたら、ぜひFPキャンプを活用してみてください。
毎日のちょっとした工夫で、経済的に余裕のある生活を手に入れましょう。
FP資格の詳細はこちらから
FP資格に関する詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
【FP資格】
▶関連記事:ファイナンシャルプランナー(FP)とは?メリット・勉強方法を徹底解説
▶関連記事:ファイナンシャルプランナー(FP)の難易度は?合格率や勉強時間を解説
【FPとして働く】
▶関連記事:40代でもファイナンシャルプランナーを目指せる?メリット・未経験向けの働き方を紹介