
24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
老後資金準備や住宅ローンの選択など、「お金の知識を学校で教えてもらいたかった…」と感じている人は多いでしょう。
2022年度から高校の授業で「資産形成」について触れられるようになりましたが、十分な知識とはいえません。
人生を豊かに過ごすためには、基盤となる6分野の知識を学び、関連性を意識する必要があるでしょう。
本記事では、FP(ファイナンシャルプランナー)の専門家であるほんださんの解説をもとに、根深い理由を解き明かします。
そして、これからの時代で「人と差がつくお金の知識」の意味と、身につけ方までお伝えします。
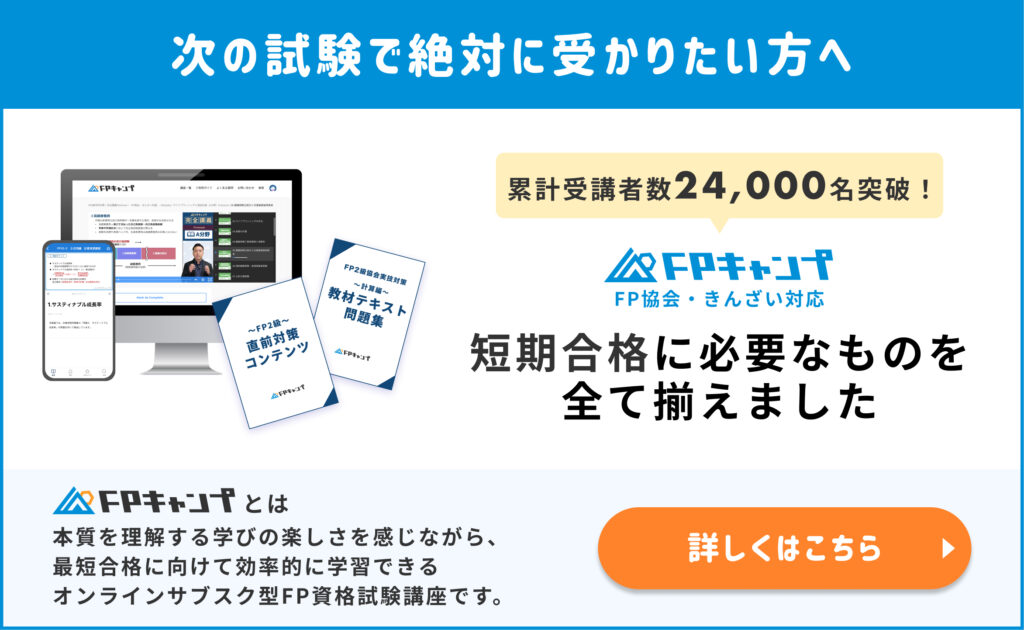
義務教育で「お金の勉強」が本格的に導入されない2つの理由
「お金の勉強を義務教育でしっかりと学ぶことは、残念ながらありえない」とほんださんが断言する背景には、国の教育の考え方が関係します。
理由①:学校は「社会ですぐ役立つこと」を教える場所ではない
学校教育は、「社会に出てすぐに役立つ知識」を教えることだけを目的としていません。
教育システムについて掘り下げて考えると、学校は国民としての共通の基盤や価値観を育む場所だといえます。
特定のスキルや実用的な金融知識を教えることは、主要な役割ではないと考えられるでしょう。
例えば、ピアノや習字のように「習いたい」という明確なニーズがあるものは、民間のサービスである習い事教室が担っています。
一方、国語・算数・歴史などの科目は、直接的な職業訓練とは異なり、国民としての教養や社会性を養うために国が提供しています。
お金の勉強も現代社会で「役立つ知識」のため、民間サービスが担っているのが現状です。
理由②:国民がお金に詳しくなると、国が困る可能性がある
国目線で考えると、国民がお金の知識を持ちすぎない方が都合がよい可能性もあります。
例えば、給料から自動的に税金が天引きされる「源泉徴収」という仕組みがあるため、国はスムーズに税金を集められます。
しかし、国民全員がFPのように税金の知識を持ち、積極的に節税対策をすれば、国の税収は減ってしまうでしょう。
義務教育に金融教育が本格的に組み込まれないのは、こうした複雑な背景があるとほんださんは考えます。
金融教育は世界の常識?海外の事例から日本の現状を考える
海外に目を向けると、多くの国では、義務教育のカリキュラムに組み込まれています。
アメリカでは無料教材で学べる環境が整っており、子どもでも挑戦できるゲームなどがあります。
イギリスでは2014年から金融教育が義務化されており、小学校を卒業するまでにお金の知識を理解していく流れです。
このように、世界では国が国民の金融リテラシー向上を支援する環境が整っており、日本の状況は対照的であるといえるでしょう。
人と差がつくお金の知識とは?
これからの時代に「人と差がつくお金の知識」は、節約術や一時的な投資テクニックではありません。
人と差をつくる知識とは、自主的に学び、資産を守り増やすための「金融リテラシー」です。
断片的な知識だけでなく、以下のような幅広いお金の知識が、あらゆる側面をカバーします。
- ライフプランニングと資金計画:人生設計にもとづいた資金準備
- リスク管理:保険や社会保障を活かしたリスクへの備え
- 金融資産運用:NISAやiDeCoなどを活用した資産形成
- タックスプランニング:税金に関する知識と節税対策
- 不動産:住宅ローンや不動産投資など
- 相続・事業承継:資産の承継に関する知識
これらの知識を網羅的かつ効率的に学ぶためには、FP(ファイナンシャルプランナー)資格の学習がおすすめです。
経済的自由を手に入れられる知識が詰まっており、未来への不安を希望に変えられます。
FP資格で学ぶ!人と差がつく知識を身につける本当の意味
義務教育でお金について学べない日本において、人と差がつくお金の知識を身につける本当の意味を解説します。
意味①:自分の力でお金の問題を解決できる
FP資格の学習を通じて幅広いお金の知識を身につければ、お金に関するさまざまな問題を自分の力で解決できるようになります。
例えば、突然の出費、教育資金や老後資金の準備など、多くの人が抱える金融の悩みに自信を持って向き合えるでしょう。
悪質な金融商品や詐欺から身を守るためのリテラシーも向上し、不要なリスクを防げるので、大切な資産を守れます。
ライフプランから見た最適な選択ができる知識があるからこそ、漠然としたお金の不安から解放され、希望に満ちた未来を選択可能です。
意味②:国が教えないからこそ「ビジネスチャンス」が生まれる
義務教育で金融教育が十分に提供されない点は、デメリットだけではありません。
別の側面から見ると、民間のサービスとして提供できる大きなビジネスチャンスが生まれることを意味します。
FPとして得た知識で、お金に関するアドバイスをしたり、情報発信をしたりするのもよいでしょう。
副業FPや独立系FPとして活動できるきっかけにもなるので、キャリアに変化を起こしたい人にも適しています。
変化の多い時代を生き抜いていくための知識を提供し、ビジネスへと発展させましょう。
意味③:親が学ぶ姿勢が、子どもの未来を変える
ほんださんは「親が学ぶ姿勢を見せなければ、子どもも勉強しない」と考えています。
親自身が勉強する姿勢を見せなければ「勉強しなさい!」と子どもにいうのは、説得力に欠けるでしょう。
親自身がFPの勉強にはげめば、子どもに知識を伝えられるだけでなく、「私も勉強を頑張ろう」と行動に移せるきっかけを作れます。
頑張っている姿を見せるからこそ、子どものやる気を刺激できるので、自ら切り開く力を養えます。
FPの知識を楽しく学ぶなら「FPキャンプ」がおすすめ
本質的なお金の知識を身につけるための最適な学習方法は、ほんださんが運営する「FPキャンプ」です。
理由①:本当に役立つ知識を学べる
FPキャンプは、単なる試験対策に留まらない、本当に役立つお金の知識を提供しています。
難しい専門用語をかみ砕いて解説してくれるため、初心者でも安心して学びを深められ、好奇心を刺激します。
FPの知識は、試験合格のためだけでなく、自身のライフプランや資産形成、節税対策など、実生活で役立つものばかりです。
しかし、暗記に頼った知識は忘れやすく、実生活にうまく当てはめられないケースが多くあります。
FPキャンプなら、本質的な知識を学べるため、悩みを具体的に解決できる応用が可能になり、問題をスムーズに解決できます。
【おすすめの記事】
FP資格の学習で学べる金融リテラシーとは?人生を豊かにする大切な知識
理由②:無料でスタートできる環境を用意
FP3級(学科試験対策)コースを無料で提供しているので、「まずは内容を試してみたい」という人でも気軽にはじめられるでしょう。
忙しい社会人や主婦でも自分のペースで学習できるよう、無期限で学習コンテンツを使えます。
学習意欲がわいた瞬間から始められ、有料コースに進むかじっくり検討できる点は、FPキャンプでしか味わえないメリットです。
【おすすめの記事】
【朗報】FP3級の独学が変わる!FPキャンプなら学科試験対策が無料で使い放題に
理由③:有料プランも低価格!1か月993円から
FPキャンプの有料プランは、高品質なFP学習コンテンツを嬉しい低価格で提供しています。
例えば、FP3級(学科・実技試験)コースは、3か月間使い放題で2,980円(税込)です。
1か月に換算しても約993円と気軽にはじめられる料金プランのため、経済的負担が気になる人にも向いています。
他社のFP講座と比較しても非常にコストパフォーマンスが高く、経済的な負担を抑えながら、確かな知識を身につけましょう。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
記事の内容を動画でチェック
本記事の内容を動画で理解したい人は、ぜひ動画もチェックしてみてください。
お金の知識は大切!自分の力でお金を守り、増やそう
義務教育ではお金の勉強が足りない現状だからこそ、自らお金の知識を身につける必要があります。
自身の力で得たお金の知識は、人生を豊かにする「人と差がつく大きな力」と変化するでしょう。
FP資格で得られる知識は、自分の力でお金の問題を解決するだけでなく、ビジネスチャンスを生み出します。
さらに、経済面だけでなく、子どもの未来にもよい影響を与える可能性を秘めています。
FPキャンプで一生役立つお金の知識を身につけ、より豊かな人生への第一歩を踏み出しませんか。
FP資格をもっと知りたい!関連記事はこちら
FP資格についてさらに詳しく知りたい人は、以下の関連記事もぜひご覧ください。
【実施団体】
【FPとして働く】










