
24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
「インフレで生活が苦しくなる」「貯金の価値が減る」などのニュースを見聞きし、漠然とした不安を感じている人は少なくありません。
インフレは、私たちの生活や資産に直接的な影響を与える、避けては通れない経済現象です。
だからこそ、仕組みを正しく理解して対策を講じなければ、知らないうちに損をしてしまう可能性があるでしょう。
本記事では、インフレの基本的な仕組みから、私たちの生活に与える影響や対策まで解説します。
さらに、根本的に資産を守り抜くための「FP資格」の知識についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
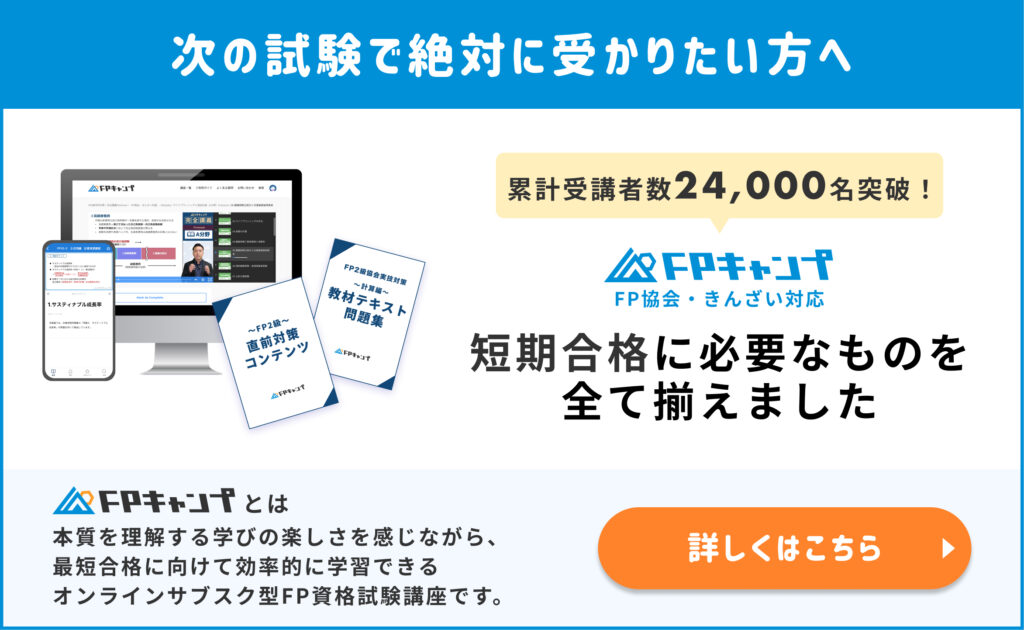
インフレとは?基本を分かりやすく解説
インフレ(インフレーション)の意味や起きる原因、メリット・デメリットを解説します。
インフレ:モノ・サービスの価値が上がる
インフレとは、「モノ・サービスの価値が上がり、お金の価値が下がること」を指します。
子どもの頃に100円で買えたクッキーが、大人になった現在では150円出さないと購入できず、驚いた経験がある人も多いでしょう。
これは、インフレが原因でクッキーの値段が上昇したためです。
「子どものころよりも多くのお金を出さないと買えなくなった」ということは、「お金の価値が下がった」という意味につながります。
つまり、インフレが進むと預貯金の実質的な価値は目減りしていくため、「インフレとともにお金が減っている」ともいえるでしょう。
仮に銀行に100万円を預けていても、世の中の物価が10%上がれば、その100万円で買えるモノの量は10%減ってしまいます。
インフレの仕組みを知り、適切な対策を取ることが、大切なお金を守るために重要です。
インフレが起きる原因
インフレが起きる主な原因は、大きく分けて2つあります。
①需要が増す
一般的には、インフレが進むと賃金が上がるため、モノやサービスを「ほしい」と思う人(需要)が増えるのが原因の1つです。
生産量(供給)を上回る状態になり、商品が次々と売れるため、企業は価格を上げても売れると判断し、物価が上昇します。
ただし、近年の日本のような「インフレしているのに賃金が増えない」という悪いインフレは、国民の生活を苦しめる要因です。
②生産コストが上がる
もう1つの原因は、生産コストの上昇です。
上記で説明した通り需要が増すと、原材料費の高騰や人件費の上昇など、生産コストが上がります。
コストをカバーするための企業による商品価格への上乗せが、物価を押し上げインフレを引き起こす原因です。
インフレのメリット・デメリット
インフレが与える、メリットとデメリットの両側面を理解しておきましょう。
メリット
「よいインフレ」の場合、企業の売上が上がるため、賃金が上がる可能性があります。
賃金が上がれば、モノやサービスを購入する人が増え、さらに企業の売上が増えるという経済の好循環が期待できるでしょう。
また、お金の価値が下がるため、借金をしている人にとっては実質的な返済負担が軽くなるという側面もあります。
デメリット
一方、物価が上昇する点は、インフレのデメリットです。食料品やガソリン価格などが上がると、家計の支出が増え、生活を圧迫します。
特に、賃金の上昇が物価の上昇に追いつかない場合、生活水準は実質的に低下するでしょう。
さらに、前述の通り、銀行預金や現金の実質的な価値が目減りするため、何も対策をしなければ、現金の価値を失っていきます。
インフレの反対はデフレ!違いを徹底解説
デフレ(デフレーション)とは、インフレとは逆に、モノやサービスの価格が継続的に下落する現象です。
「モノの価値が下がり、お金の価値が上がる」状態になり、「もう少し待てば、もっと安く買えるかもしれない」と考える人が増えます。
結果、買い物を控える人が多くなり、モノが売れずに企業の売上は減り、従業員の給与を下げたり、リストラを行ったりせざるを得ません。
収入が減った家計はさらに消費を切り詰め、悪循環に陥りやすくなり、これを「デフレスパイラル」と呼びます。
インフレが与える3つの影響とは
インフレ時に注意すべき3つの具体的な影響について解説します。
①食費や光熱費が上がり、家計を圧迫する
最も身近な影響は、日々の生活コストの上昇です。スーパーでの買い物や、毎月の電気・ガス代の請求額が以前よりも高くなっていると感じる場面が増えるでしょう。
これらの支出は生活に不可欠なものであるため、節約にも限界があります。物価上昇のペースに収入の増加が追いつかなければ、家計は確実に圧迫されていきます。
②銀行預金や学資保険などの価値が目減りする
現在の低金利では、インフレ時に普通預金や定期預金に預けていても、ほとんど利息がつきません。
インフレ率が預金金利を上回らない限り、預金の価値は実質的に減り続けてしまいます。
また、将来のために備えている学資保険や個人年金保険なども同じデメリットがあるため、注意が必要です。
満期時に受け取る金額が決まっている保険商品は、契約時よりも受け取る保険金の価値が目減りしている可能性があります。
③よいインフレなら賃金が上がる
インフレは、必ずしも悪い影響ばかりではありません。
経済の好循環から生まれる「よいインフレ」であれば、企業の業績が向上し、従業員の賃金上昇に反映されます。
自身の収入が増えることで、生活水準を維持/向上させられるため、より豊かな生活を過ごせるでしょう。
FPが解説!今すぐはじめられる4つのインフレ対策
インフレから資産を守るための、4つの対策を紹介します。
①NISAやiDeCoを活用して資産運用をはじめる
インフレ対策では、インフレ率を上回るリターンが期待できる資産を保有するのが基本です。
例えば、注目度が高い新NISAを利用できる、株式投資や投資信託などが挙げられます。
NISA(少額投資非課税制度)とは、専用の非課税口座内で得た利益が非課税になる制度です。
税金のことを気にせず資産運用をはじめられるため、気軽にインフレ対策ができます。
損失を避けるために、長期・積立・分散で運用し、資産形成を進めましょう。
②ゴールドや不動産などの資産を持つ
ゴールド(金)や不動産といった資産は、インフレに強い資産として有名です。
これらの実物資産は、インフレでお金の価値が下がっても、価値が下がりにくい、あるいは上昇する傾向があります。
資産の一部を実物資産として保有しておけば、通貨の価値が下落したときに有効でしょう。
ただし、価格変動リスクや流動性(換金のしやすさ)などのデメリットもあるため、資産全体の中でのバランスを考えるのが重要です。
③日本円以外の資産を持つ
資産をすべて日本円で保有していると、日本のインフレや円安が進行した場合に、直接ダメージを受けてしまいます。
インフレすると円安しやすく、円安になるとインフレしやすくなるため、影響を減らすためには外貨資産が重要です。
例えば、米ドルやユーロなどの外貨資産(外貨預金・外国株式・外国債券など)を保有し、複数の通貨に分散させる方がよいでしょう。
異なる値動きをする通貨を組み合わせることで、特定の通貨価値が下がったとしても、他の通貨でカバーできる可能性があります。
④お金の知識を身につける
①~③で紹介した対策は非常に有効ですが、インフレ対策を柔軟に進めるには、土台となる「お金の知識」が不可欠です。
経済の状況は常に変化するため、リスク管理方法や最適な金融商品などを慎重に見極めなければなりません。
個人の年収や家族構成などの条件によって最適なバランスは異なり、損失が出ても生活に支障がない方法を選ぶ必要があります。
他人の意見に流されず、自身で判断する力を養うことこそが、根本的なインフレ対策といえるでしょう。
お金の知識を学ぶなら「FP資格」がおすすめ!3つの理由
お金の知識を「使える知識」として学びたい人におすすめなのが、「ファイナンシャル・プランナー(FP)」資格の学習です。
①幅広いお金の知識が得られる
FP資格の勉強では、以下の6分野にわたるお金の知識を網羅して学べます。
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
これらの知識は、インフレ対策で紹介した株式投資や不動産投資などに関わる内容です。
断片的な知識とは違い、幅広い知識があれば、自分や家族の状況に合わせたプランを自身で考えられるようになります。
大切な資産を守り、リスクを軽減させながら増やせる方法こそが、正しいお金の知識を得ることだといえるでしょう。
②インフレの仕組みを理解できる
FPの学習では、景気動向指数や物価指数といった経済指標の読み解き方も学びます。
専門用語の意味を理解できていれば、現在の経済がインフレなのかデフレなのか、なぜ起きているのかを理解可能です。
SNSの情報をうのみにせずに、自分が今必要な対策を進められるので、安心して毎日を過ごせます。
経済の仕組みを理解すれば、インフレを恐れることなく、冷静かつ客観的な視点で考えられるでしょう。
③専門家に相談する費用を節約できる
お金に関する知識がなければ、金融商品の購入や保険の見直しなどを、金融機関の担当者や専門家に頼らざるを得ません。
ケースによっては、本当に最適な商品よりも企業の売上につながる商品を提案されるなどの可能性があります。
また、お金の専門家であるFPに相談する場合、多くのケースでは相談料が発生するため、回数を重ねれば負担を感じるでしょう。
しかし、FPの知識があれば、自身で必要な情報を収集し、本当に必要な選択ができる知識の基盤が身につきます。
聞きなれない専門用語が多く登場するため、難しく感じるかもしれませんが、FP知識が身につけば、悩みの根本解決が可能です。
分かりやすさ重視ならFPキャンプ!本質学習で悩みを解決
FPの学習に興味を持った人におすすめしたいのが、FP解説で人気のほんださんが運営する学習コンテンツ「FPキャンプ」です。
魅力①:本質学習だからこそ、生活に活かせる
FPキャンプでは、試験合格のためだけの暗記学習ではなく、実生活で本当に使える「本質的な知識」が会得可能です。
YouTubeチャンネル登録者数31万人超えを誇る「ほんださん」が、複雑な制度を分かりやすくかみ砕いて解説します。
「なぜそうなるのか」という本質から理解できるので、経済の変化が激しい時代でも応用できる、一生モノの知識を得られるでしょう。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
魅力②:無料プランあり!有料プランのコスパも抜群
「いきなり有料は不安」という人でも、FPキャンプなら安心してはじめられます。
FP3級の学科試験範囲を網羅した「3級合格パック」は、無料で利用可能です。
講義の分かりやすさや使い勝手を、自身でじっくりと体験できるのは、FPキャンプならではでしょう。
また、有料プランも非常にリーズナブルに設定されており、コストパフォーマンスは抜群です。
まずは無料プランでFP学習の効果を実感し、自身の資産を守るための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
まとめ|インフレ対策は必須!お金の知識で悩みを希望に変えよう
インフレは、私たちの意思とは関係なく、大切な資産の価値が静かに減っていく現象です。
しかし、インフレを正しく理解し、適切な対策をすれば、決して怖いものではありません。
反対に、自身の資産を見直し、よりよい未来を築くためのきっかけとして役立ちます。
資産をインフレから守り、インフレの恩恵を受けるためには「お金の知識」が不可欠です。
FP学習を通じて得られる体系的な知識は、これからの時代を生き抜くための基盤となります。
まずはFPキャンプの無料コースから、学習をはじめてみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい!FP資格の関連記事
FP資格の関連記事を紹介しますので、ぜひご覧ください。
【FP資格】
▶関連記事:ファイナンシャルプランナー(FP)とは?メリット・勉強方法を徹底解説
▶関連記事:ファイナンシャルプランナー(FP)試験は独学でも合格できる?勉強法・テキストなどを解説!
【FP資格の活かし方】
▶関連記事:ファイナンシャルプランナーの仕事内容とは?働き方や年収を詳しくガイド
▶関連記事:ファイナンシャルプランナーの働き方は柔軟!企業系・独立系・副業について解説










