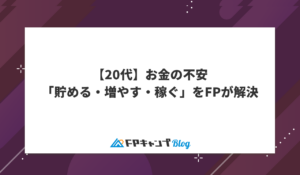24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
「将来のためにお金を増やしたいけど、投資はなんだか怖い…」と感じている人は多いのではないでしょうか。
投資と聞くと、専門知識が必要でリスクが高いイメージがあるかもしれません。
しかし、正しい知識を身につければ、投資はあなたの資産をインフレなどのリスクから守り、資産を育てるための味方になります。
投資に伴うリスクを正しく理解し、自分に合った方法ではじめるためには、ファイナンシャルプランナー(FP)の勉強がおすすめです。
本記事では、投資の基本的な仕組みから貯金との違い、FP資格がなぜ投資に有利なのかまで、分かりやすくFPが解説します。
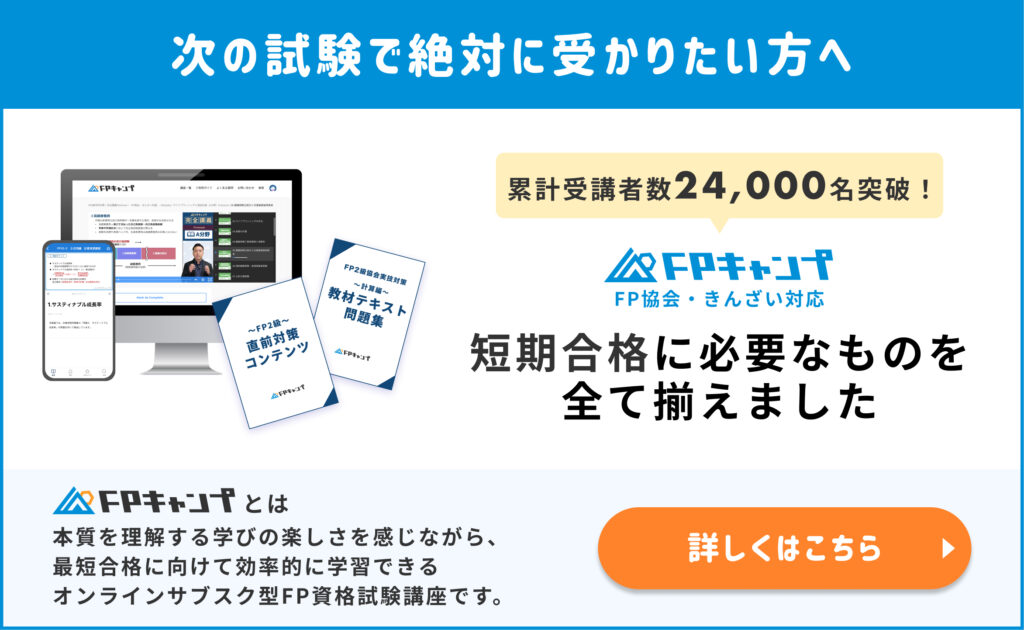
投資とは?貯金との違いも簡単に解説
投資の基本的な考え方と、貯金との明確な違いを解説します。
投資は、資産を守り増やす方法
投資とは、利益(リターン)を見込んで、自分のお金を株式や不動産などの「資産」に換える方法です。
うまく活用できれば、自分のお金自身にお金を稼いでもらえるため、「不労所得」とも呼ばれています。
前述通り、銀行にお金を預けているだけでは、お金は眠っている状態と変わりません。
しかし、将来成長が期待できる企業の株式や、投資信託などの資産を運用すれば、2種類のリターンを得られます。
投資には元本が保証されない「リスク」が伴いますが、投資の世界でいう「リスク」とは、単なる「危険」という意味ではありません。
損する可能性も得する可能性もある、「リターンの不確実性(振れ幅)」を指します。
リスクを正しく理解した上で、後述するリスクを軽減させる方法を活用し、コントロールすれば、過度に恐れる必要はないでしょう。

2種類のリターンの詳細は、後ほど解説します!
貯金と投資の違い
投資と貯金は、お金を将来のために備えるという点で似ていますが、目的と特徴は根本的に異なります。
貯金と投資の違いを以下の表で比較しました。
| 貯金 | 投資 | |
|---|---|---|
| 目的 | お金を蓄える | お金を増やし守る |
| リターン | 低金利のため、ほぼ0 | リターンを期待できる |
| リスク | 元本保証 →預けていてもお金は減らない | 元本割れの可能性あり →購入した金額より価値が下がるケースがある |
| インフレ | インフレに弱い →お金の価値が目減りする | インフレに強い商品が多い →インフレとともにお金が増えやすい |
投資する金融商品によってリターンやリスクなどは異なりますが、貯金よりも資産を増やしやすい傾向にあります。
貯金のメリットは、元本が保証されている安全性です。
近い将来に使う予定のあるお金(結婚資金や教育費)や、万が一のための生活防衛資金(生活費の6か月~1年分)を確保するのに適しています。
一方、投資は当面使う予定のない余裕資金で、長期的な視点でお金を大きく育てたい目的と相性がよいでしょう。
「守りの貯金」と「攻めの投資」、それぞれの役割を理解し、貯金で足元を固めた上で、余裕資金を投資にまわすのが賢い選択です。
投資が必要な3つの理由を解説
投資は一部のお金持ちだけのものではなく、将来の資産を築くために多くの人にとって効果的な手段です。
理由①:低金利が原因でお金が増やしにくい
過去には金利がよい時代もありましたが、現在の金利は非常に低く、メガバンク(2025年9月時点)の普通預金の金利は年率0.2%です。
銀行に100万円を預けていても、1年で得られる利息はわずか2,000円のため、お金を増やす手段として銀行預金はおすすめできません。
一方、投資は低金利時代でも資産形成していくための手段として、優れた金融商品だといえるでしょう。
理由②:インフレによりお金の価値が下がる
子どもの頃に100円で買えたお菓子が、現在では150円に値上げされ、驚いたことがある人も多いのではないでしょうか。
インフレ(インフレーション)とは、前述のお菓子のように、物価が上がり続けている状態を指します。
100円で買えたお菓子が150円出さないと買えないのは、「お金の価値が下がった」という意味です。
例えば、物価が年2%上昇すれば、今まで100万円で買えたものが102万円なければ買えなくなり、今ある100万円は約98万円に目減りします。
基本的にはインフレしていくと考えられており、インフレによるお金の価値の低下を防ぐ必要があるでしょう。
投資では、インフレを味方につけられる金融商品があるため、自身の資産を増やし守るためには、必要な手段です。
理由③:将来への資産準備
少子高齢化による公的年金制度への不安や、終身雇用制度の崩壊による退職金の減少など、多くの人が不安を感じているでしょう。
これまでの日本とは違い、国や会社に頼るだけでは豊かな老後を送りづらい時代に変化しています。
将来の不安を解決するためには、投資を有効活用し、時間をかけて資産形成を進めなければなりません。
インフレに負けないようにお金を育て、自分の力で資産を守り増やすための「投資」の知識が不可欠です。
投資で得られるリターンは2つ!全体像を把握しよう
投資で得られる利益(リターン)には、大きく分けて2つの種類があります。
インカムゲイン
インカムゲインとは、資産を保有している間、継続的に得られる収益のことです。
例えば、株式投資における配当金や、不動産投資における家賃収入、銀行預金の利息などが当てはまります。
一度に大きな利益を得る訳ではありませんが、定期的かつ安定的に収入を得られるのが特徴です。
お金がリターンを生み出し続けてくれるので、長期的な資産形成に役立つでしょう。
株式の配当金は、企業の業績に応じて支払われ、保有しているだけでリターンが積み上がっていくため、不労所得としても人気があります。
キャピタルゲイン
キャピタルゲインとは、保有している資産の価値が購入時よりも上がったときに、売却して得られるリターンを指します。
例えば、10万円で購入した株式が15万円に値上がりしたタイミングで売却すれば、差額の5万円がキャピタルゲインです。
インカムゲインとは対照的に、1度の取引で大きな利益を狙える可能性があります。
ただし、価格が下落したときに売却すれば、損失(キャピタルロス)が発生するリスクもあるため、十分に注意しなければなりません。
キャピタルゲインやインカムゲインを再び投資にまわすことで、利益が利益を生む「複利の効果」が働きます。
※複利:得たリターンも投資に回すこと
時間をかければかけるほど、雪だるま式に資産が大きくなる効果が期待できるでしょう。
投資にはどんな種類がある?代表的な4つの金融商品を解説
投資にはさまざまな金融商品が存在するため、初心者がまず知っておきたい代表的な4つの商品について詳しく解説します。
①株式
株式投資は、株式会社が資金調達のために発行する「株式」を売買する投資です。
株主になると、配当金を受け取ったり(インカムゲイン)、株価が上昇したときに売却して利益を得たり(キャピタルゲイン)できます。
企業によっては、自社製品やサービスを受けられる株主優待もあり、注目を集めている金融商品です。
ネット証券などで証券口座を開設すれば、スマホやPCから簡単に売買できます。
通常は100株単位(単元株)での取引ですが、1株から購入できる証券会社もあるので、数千円からの少額投資も可能です。
【どんな人におすすめ?】
- 特定の企業を応援したい人
- 値上がり益や配当金、株主優待に魅力を感じる人
②債券
債券は、国や地方公共団体、企業などが資金を借り入れるために発行する「借用証書」のようなものです。
購入すると、定期的に利子を受け取れ、満期日(償還日)を迎えると元本が返還されます。
また、償還日より前に売却することも可能で、そのときの時価によっては売却益(キャピタルゲイン)も狙えるでしょう。
株式に比べて価格変動のリスクが低く、安全性が高いのが特徴で、コツコツと資産形成をしたい人に向いています。
日本国が発行する個人向け国債は、「元本割れなし」と公式サイトで公表されており、安全性を重視したい人に最適です。
【どんな人におすすめ?】
- 元本割れのリスクをできるだけ避けたい人
- 決まった利息収入を得たい人
③投資信託
投資信託は、多くの投資家から集めた資金をひとまとめにし、運用の専門家(ファンドマネージャー)が運用する金融商品です。
1つの投資信託の中にさまざまな資産が含まれているため、投資信託を購入するだけで自然と分散投資になり、リスクを軽減できます。
ネット証券では、月々1,000円からはじめられ、投資初心者におすすめの方法です。
日経平均株価や米国のS&P500などの指数に連動する「インデックスファンド」は、手数料が安く、人気があります。
【どんな人におすすめ?】
- 投資初心者
- 少額から積立投資をはじめたい人
- 自分で投資先を選ぶのが難しいと感じる人
④不動産・REIT(不動産投資信託)
不動産投資とは、マンションやアパートなどを購入し、家賃収入や売却益を狙う方法を指します。
一方で、「REIT(リート)」は投資信託のため、多額の資金がなくても間接的に不動産投資が可能です。
【どんな人におすすめ?】
- 不動産投資・REIT:安定したインカムゲインが欲しい人
- REIT:不動産に興味があるが、多額の資金を用意するのは難しい人
投資の注意点|知識がないと大きな損失につながるリスクも
投資をする上で、忘れてはならないのが「リスク」の存在です。
正しい知識を持たずに投資をはじめてしまうと、大きな損失につながる可能性があります。
金融商品の価格は常に変動しており、時には急激な下落も起こりえるため、基盤となるお金の知識は重要です。
価格が下がったときに冷静な判断ができず、恐怖心から慌てて売却して大きな損失につなげてしまう可能性もあるでしょう。
こうした失敗を避けるための投資の基本原則が、「長期・積立・分散」です。
長期投資をすれば、前述の複利を活用できるので、資産を増やしやすい傾向にあります。
リスクを軽減できる各投資方法の特徴は、以下の通りです。
- 長期投資
短期的に価格が下落した場合でも、5年後・10年後という長いスパンで考えれば、価格が上昇するタイミングを待てます。
期間が長いほど、リターンのばらつきが小さくなりやすく、リスクを軽減させるための重要ポイントです。
また、長ければ長いほど複利の力が大きくなるメリットもあり、資産を増やす味方になるでしょう。
- 積立投資
低価格から投資をはじめやすく、自動積み立てもできるため、着実に資産を増やせます。
また、買うタイミングを分散させられ、ドルコスト平均法の恩恵も受けられる点は、大きなメリットといえるでしょう。
ドルコスト平均法とは、定期的に一定額を購入し続けることで、最終的な平均価格が安くなることを指します。
資産形成を進める上で役立つため、把握しておくのがおすすめです。
- 分散投資
複数の金融商品を保有すれば、リスクを分散させられます。
例えば、A社の株式しかない場合、A社が経営不振になると100%の打撃が来るでしょう。
しかし、A社・B社・C社の株式があれば、1/3のダメージに軽減できます。
リスクを軽減させる方法として、分散投資も非常に重要です。
▶関連記事:【FPが解説】投資の勉強はFP資格が最短ルート!遠回りしないはじめ方
なぜFP資格が投資に有利?リスクを減らせる3つの理由
FPの学習がなぜ投資に有利に働くのか、3つの理由を解説します。
理由①:お金の知識を体系的に学べる
FP資格の学習では、金融資産運用の知識だけでなく、お金に関する6つの分野を網羅的・体系的に学べます。
試験範囲は、以下の通りです。
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
これらの知識を学ぶからこそ、本当に自分に合う金融商品を選べ、手取り額を上げるための節税対策ができるでしょう。
他にも、加入している保険を見直し、保険料の差額を投資に回せば、資産形成のスピードをあげられます。
FPの学習を通じてお金の全体像を把握することで、より多角的で有利な投資判断が可能です。
理由②:自分に合う金融商品・ポートフォリオが分かる
FPの学習では、さまざまな商品のリスクとリターンの関係を学び、自身の年齢や家族構成に合う運用方法を選ぶ力を養います。
そのため、自分のリスク許容度が分かり、無理のない投資ができるでしょう。
リスク許容度とは、損失に耐えられる範囲を指し、個人の状況に合わせて異なるため、しっかり見極めなければなりません。
例えば、100万円の損失に耐えられる、独身で十分な貯金があるAさんが、養う家族が多く貯金が少ないBさんに商品を勧めたとします。
この場合、価格が下落すると、AさんよりもBさんのダメージは非常に大きく、生活に支障が出る可能性があるでしょう。
また、株式や債券など値動きの異なる資産を組み合わせる「ポートフォリオ」の重要性も理解できるのが、FP資格です。
市場が暴落したときでも資産全体へのダメージを和らげ、リスクに強い資産配分を考えられるようになります。
自分自身の資産を増やし守るためには、リスク許容度を把握し、リスクを軽減させる組み合わせが重要です。
理由③:税金を理解でき、手取り金額を増やせる
投資で得たリターンは課税されるため、手取り額を多くするためには、税金の知識が不可欠です。
投資で得た利益には20.315%の税金がかかるため、リターンが100万円の場合は203,150円の税金がかかり、手取り額は約796,850円です。
しかし、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を使えば、利益が非課税になる優遇を受けられます。
先ほどの例えを使うと、100万円そのまま受け取れ、老後資金や教育資金などに活用可能です。
FPの学習では、国民がお得に投資できる非課税制度の仕組みや効果的な活用法を深く理解できます。
知っているか知らないかで将来の資産額に大きな差が生まれる、大切な知識でしょう。
投資に役立つ知識を身につけるなら、FPキャンプが最短ルート
投資で失敗しないための「生きた知識」を効率的に身につけたい人には、FP解説で人気のほんださんが運営するFPキャンプが最適です。
魅力①:試験と投資に活かせる本当の知識を学べる
FPキャンプでは、試験合格のためだけの丸暗記をさせない「本質理解」を重視した教材を提供しています。
「なぜこの制度があるのか?」という背景や目的から学ぶため、知識が深く記憶に定着しやすく、応用問題にも対応可能です。
本質を理解しているからこそ、法改正があったときや実生活で知識を使う場合もスムーズに対応できます。
FPキャンプで得られる知識の深さは、「一生モノの金融リテラシー」として、人生を支える基盤になるでしょう。
正しいお金の知識と判断力を指す、金融リテラシーが大切な理由を以下の記事にて紹介しています。ぜひご覧ください。
▶関連記事:FP資格の学習で学べる金融リテラシーとは?人生を豊かにする大切な知識
魅力②:自己投資に最適なお手頃価格
FP3級対策は、31日間使い放題で990円(税抜)からはじめられるハードルの低さも、FPキャンプの魅力です。
通常、FP3級対策をスクールやオンライン講座でする場合、約2万円の受講料と入会金がかかります。
しかし、FPキャンプは入会金がかからず、学習に必要なテキスト・問題集・講義動画などが自由に利用可能です。
ユーモアを交えたほんださんの講義は、勉強が苦手な人でも楽しめる内容のため、安心して学習できるでしょう。
投資をはじめる前の自己投資として、コストパフォーマンスのよい選択の1つだといえます。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
魅力③:質の高さも妥協しない、ハイレベルクオリティ
お手頃な価格でありながら、講義の質に一切の妥協はありません。
公式サイトに掲載された多数の合格者の声が、FPキャンプのコンテンツの質の高さを物語っています。
また、FP2級試験(2025年1月実施)では、全体平均の合格率を大きく上回りました。
全体平均とFPキャンプの合格率は、以下の通りです。
| 対象試験 | 全体平均 | FPキャンプ生 |
|---|---|---|
| 学科試験 日本FP協会・きんざい | 31.6% | 87.8% |
| 実技試験 日本FP協会 (資産設計提案業務) | 48.8% | 92.6% |
| 実技試験 きんざい (個人資産相談業務) | 45.1% | 89% |
| 実技試験 きんざい (生保顧客資産相談業務) | 43.1% | 100% |
効率よく最短ルートでお金の知識を学びたい人にこそ、活用していただきたいコンテンツがFPキャンプです。
詳しい内容は、FPキャンプの公式サイトをご覧ください。
まとめ|FP資格でリスク減!投資を成功させる武器を手にしよう
低金利やインフレが進む現代において、投資は将来の資産を守り・増やすための重要な手段です。
しかし、知識という武器を持たずに投資の世界に飛び込むのは、大きなリスクを伴います。
FPの学習を通じて得られるお金の知識は、自分と相性のよい投資法を選択できる基盤になるでしょう。
投資のリスクを正しく理解し、コントロールする力を身につけることで、自信を持って資産形成の一歩を踏み出せるようになります。
FPキャンプなら、質の高い学びを驚きの価格ではじめられるので、未来への自己投資としておすすめです。
FPの知識を学び、投資を成功させるための「武器」を手に入れてみませんか。