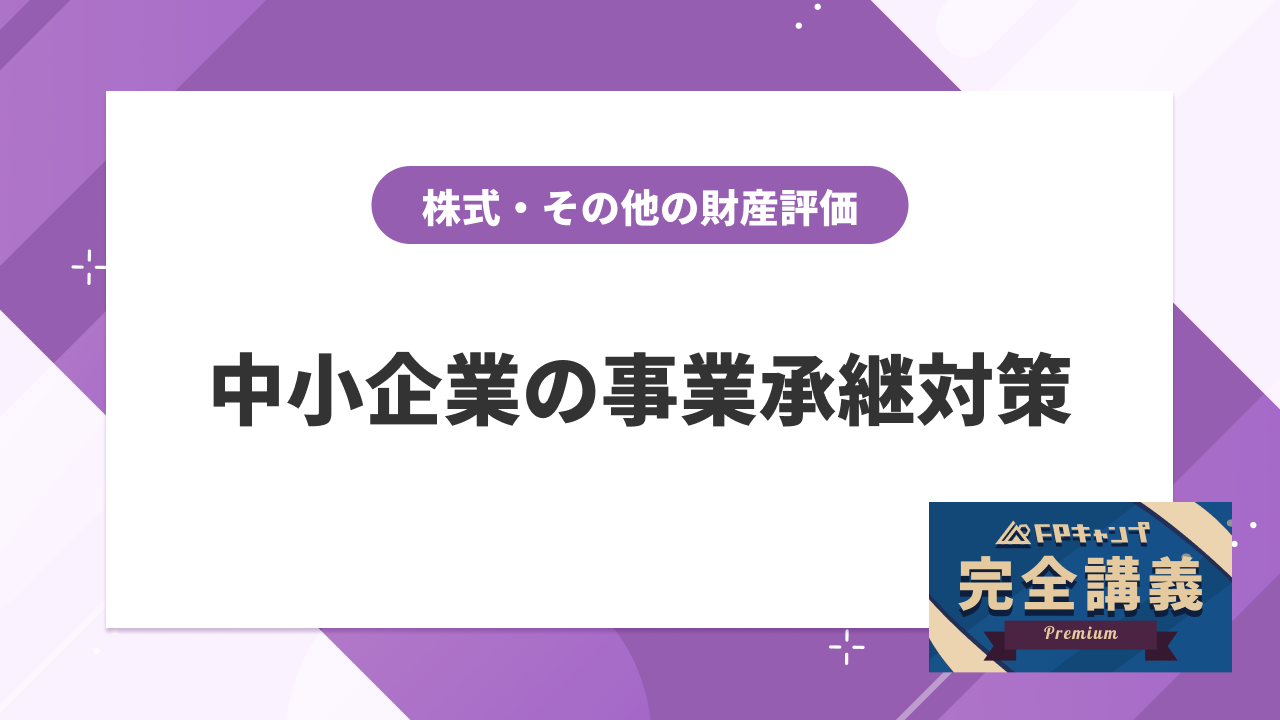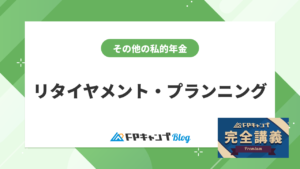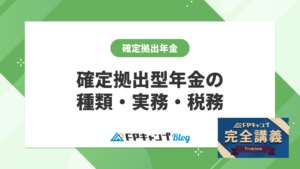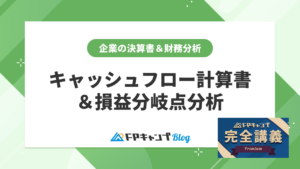24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
中小企業の経営者の方々にとって、事業承継は将来の企業の存続を左右する重要な課題です。
また、FP2級の試験対策としても、事業承継に関する知識は必須です。
相続税や贈与税、そして会社法など、関連する法律や制度は複雑で、どこから手をつければ良いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、FP2級の試験範囲も踏まえながら、中小企業の事業承継対策、特に退職金と保険の活用について、分かりやすく解説していきます。

事業承継対策って、具体的に何をすればいいのでしょうか?相続税の計算も複雑そうで不安です…



そうですね、事業承継は複雑な要素が多いので、不安になるのも当然です。この講座で、中小企業における事業承継対策の基礎をしっかり理解し、FP2級合格を目指しましょう!


中小企業の事業承継対策の重要性
なぜ事業承継対策が必要なのか? FP2級でも押さえておくべきポイント
中小企業の事業承継は、単に経営者の交代を意味するだけでなく、企業の存続、従業員の雇用、そして地域経済にも大きな影響を与えます。
後継者不足、相続税の負担、経営ノウハウの継承など、様々な課題が存在します。
だからこそ、早めに対策を講じることが重要です。
FP2級の試験でも、事業承継対策に関する問題は頻出です。
中小企業経営の現状や課題、そして具体的な対策方法について理解を深めていきましょう。



事業承継対策を怠ると、どんな問題が起こるのでしょうか?



後継者不在による廃業や、多額の相続税による資金繰りの悪化など、企業の存続を脅かす深刻な事態に陥る可能性があります。早めの対策が肝心ですよ。
退職金活用による事業承継対策
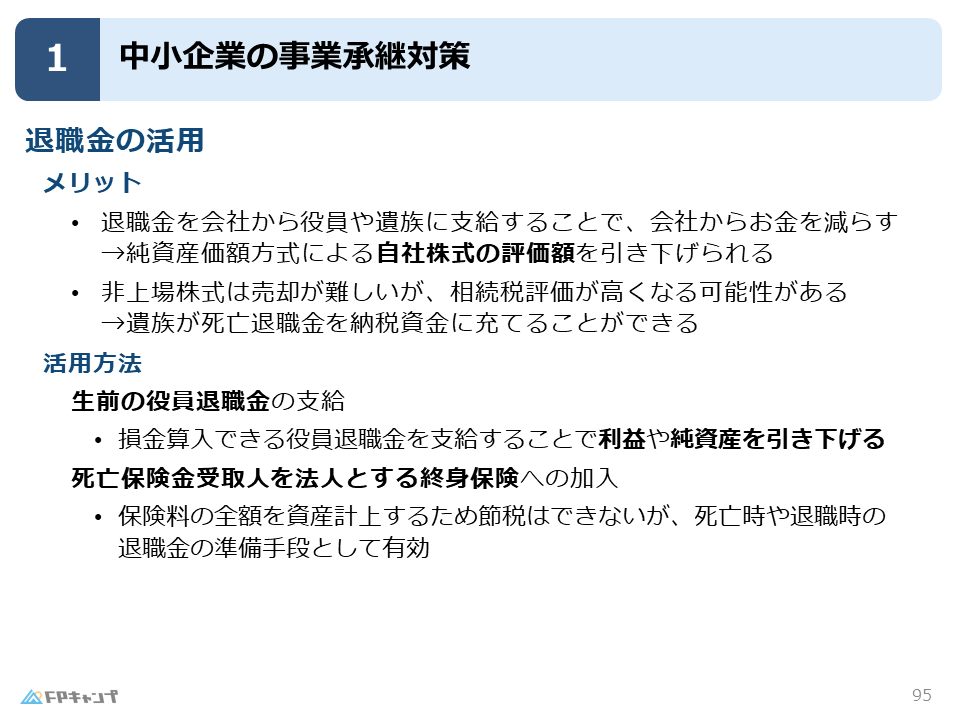
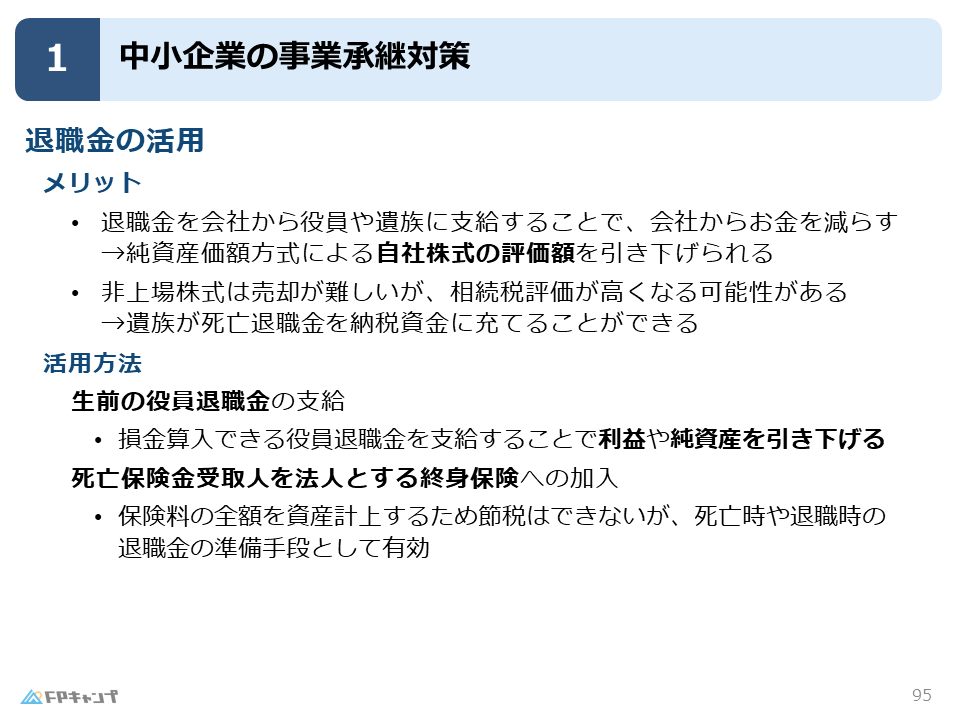
退職金で会社のお金を有効活用! そのメリットとは?
中小企業の社長にとって、退職金は事業承継対策において非常に有効な手段です。
会社にお金が留まっている状態よりも、退職金として社長個人に支払うことで、様々なメリットが生まれます。
会社からお金を出すことで、会社の純資産価額を下げ、相続税評価額を抑制することができます。
また、社長個人が資金を自由に使えるようになるため、事業承継のための資金として活用することも可能です。
相続税対策にも有効な退職金! 納税資金確保の重要性
相続税の納税資金の確保は、事業承継における大きな課題です。
特に非上場株式を相続する場合、換金性が低いため、多額の相続税を支払うことが困難になるケースも少なくありません。
そこで、死亡退職金を設定しておくことで、遺族は相続税の納税資金をスムーズに確保することができます。
これも退職金を活用する大きなメリットの一つです。



退職金って、単にお給料の延長線上にあるものと考えていましたが、事業承継にも役立つんですね!



その通りです!退職金は、会社の財産を個人に移転させる効果的な手段であり、計画的に活用することで、スムーズな事業承継を実現できます。
非上場株式相続の課題と解決策
売却困難な非上場株式、その評価額と相続税への影響
中小企業の非上場株式は、株式市場で取引されていないため、売却が難しく、換金性が低いという特徴があります。
しかし、相続税評価額は会社の業績や資産状況に応じて算出されるため、高額になる場合があり、多額の相続税が発生する可能性があります。
取引相場のない株式の評価は複雑で、FP2級の試験でも重要なポイントです。
しっかりと理解しておきましょう。
死亡退職金で相続税の納税資金を確保!
前述の通り、死亡退職金を設定しておくことで、非上場株式を相続した場合でも、遺族は相続税の納税資金を確保することができます。
M&A(企業の合併・買収)などで株式を売却することも選択肢の一つですが、時間と手間がかかるため、死亡退職金による納税資金の確保は非常に有効な対策となります。



非上場株式の相続は、売却が難しいという点が大きな課題なんですね。M&Aも選択肢としてはあるんですね。



はい、その通りです。M&Aは会社の規模や業種によっては有効な手段ですが、中小企業の場合は必ずしも容易ではありません。死亡退職金は、より現実的な解決策と言えるでしょう。
退職金の活用方法
生前贈与としての役員退職金、損金算入のメリット
社長が生きている間に役員退職金を支払うことで、会社の純資産額を減らし、相続税対策を行うことができます。
また、役員退職金は、法人税の計算上、損金算入が認められるため、会社の節税にも繋がります。
生前贈与と組み合わせることで、より効果的な相続税対策が可能となります。
会社の利益と純資産額を減らす効果的な方法とは
役員退職金を支給することで、会社の利益を減らし、ひいては純資産額を減少させることができます。
これは、取引相場のない株式の評価額を下げることに繋がり、結果として相続税の負担軽減に繋がります。
計画的に役員退職金を利用することで、効果的な事業承継対策を実現できます。



役員退職金を活用することで、会社の節税と相続税対策の両方ができるんですね!



まさに、一石二鳥の対策と言えるでしょう。ただし、税務上のルールをしっかりと理解した上で、適切に運用することが重要です。
保険活用による事業承継対策
死亡保険金で退職金を準備! 生命保険の活用法
生命保険を活用することで、死亡退職金を準備することができます。
終身保険や生命保険の受取人を法人とすることで、万が一の場合に備えることができます。
また、保険料の一部は損金算入できる場合があり、節税効果も期待できます。
リスク管理と事業承継対策を同時に実現できる有効な手段です。
まとまった資金確保に役立つ保険! リスク管理との関連性
生命保険は、死亡や高度障害といったリスクに備えるだけでなく、事業承継対策にも有効です。
死亡保険金を受取人である法人へ支払うことで、まとまった資金を確保し、事業承継に活用することができます。
保険料の支払いや受取方法などを適切に設計することで、リスク管理と事業承継対策を効率的に行うことができます。



保険を活用することで、リスク管理と事業承継対策を同時に行えるのは魅力的ですね!



その通りです!保険は、事業承継における様々なリスクに備えるための強力なツールとなります。目的に合わせて最適な保険を選ぶことが大切です。
中小企業の事業承継対策まとめ:退職金と保険でスムーズな承継を実現!
中小企業の事業承継対策において、退職金と保険は非常に重要な役割を果たします。
退職金は会社の純資産価額を調整し、相続税対策に有効です。
また、死亡退職金は相続税の納税資金を確保する手段として重要です。
保険は、死亡や高度障害といったリスクに備えるだけでなく、事業承継に必要な資金を確保するのにも役立ちます。
これらのツールを効果的に活用することで、スムーズな事業承継を実現しましょう。
| 対策 | メリット |
|---|---|
| 退職金 | 純資産価額の調整、相続税対策、納税資金確保 |
| 保険 | リスク管理、事業承継資金の確保 |



退職金と保険の活用法、よく理解できました!FP2級の試験対策にも役立ちそうです。



素晴らしい!事業承継対策は、FP2級試験でも重要なテーマです。しっかりと理解しておけば、合格に大きく近づくはずです。頑張ってください!