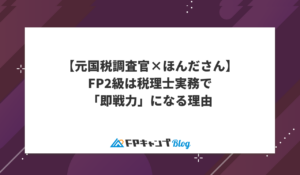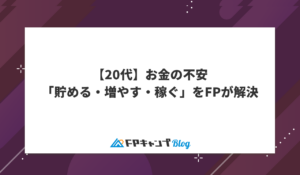24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
将来への不安から「資産運用」の必要性を感じているものの、「難しそう」「損をしそうで怖い」と抵抗を感じる人は多いでしょう。
しかし、貯蓄だけで資産を守ることが難しい現代において、資産運用は重要な選択肢です。
本記事では、初心者が失敗のリスクを抑えるための「長期・積立・分散」の三原則を徹底解説します。
さらに、押さえておきたい5つのポイントや金融リテラシーの重要性について解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
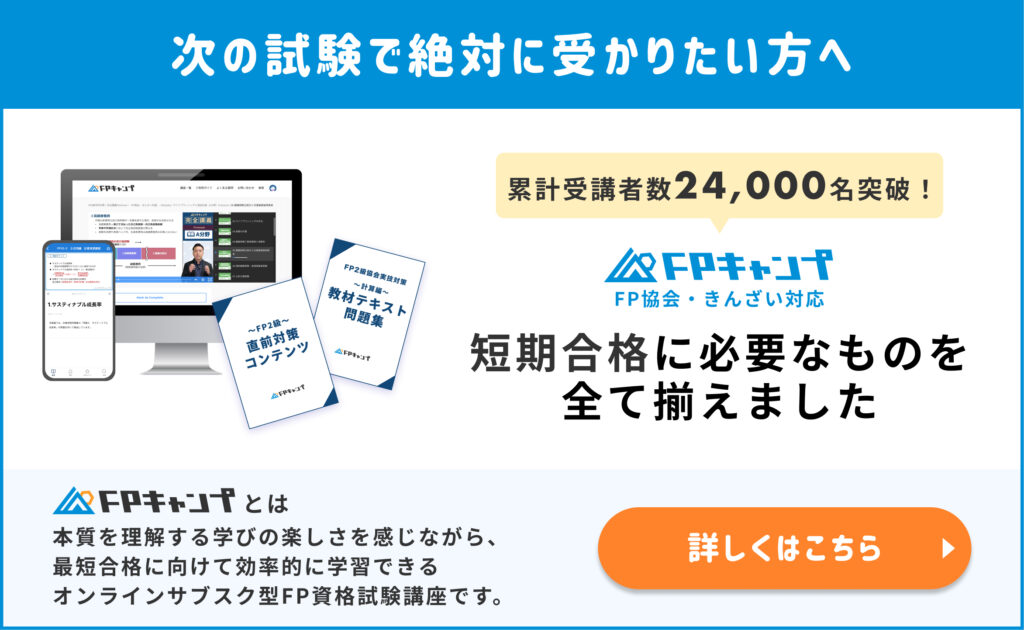
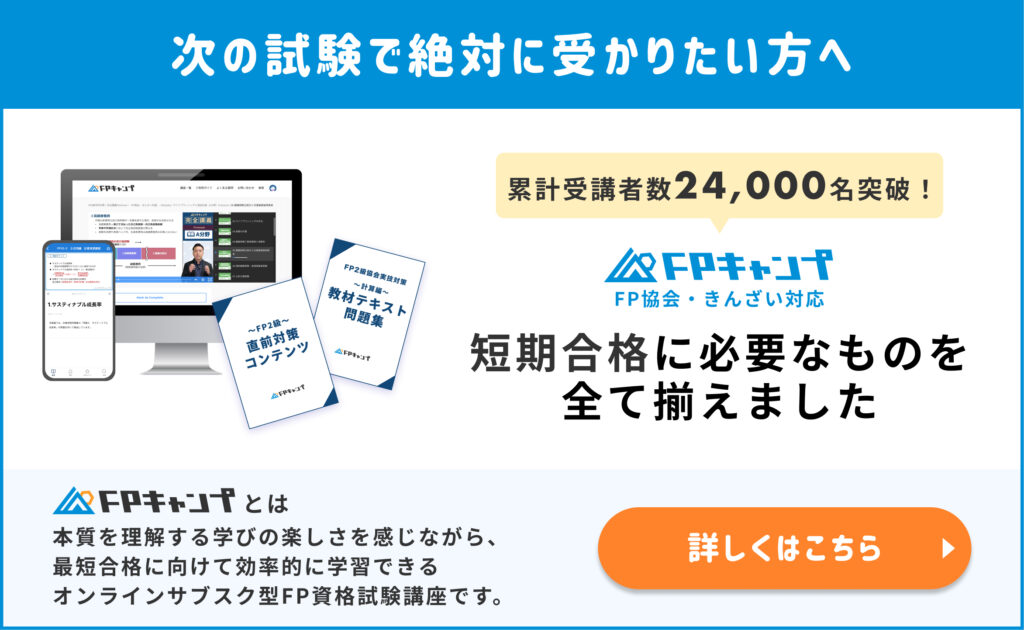
資産運用の必要性
結論、現代の日本において資産運用の必要性は非常に高まっています。
これまでの日本は、デフレ(デフレーション)だったため、貯蓄は資産を守る手段の一つでした。
デフレとは、物価が下がり続け、お金の価値が上がっていく状態を指します。
しかし、現在の日本はインフレ(インフレーション)しており、貯蓄するだけでは、お金の価値が下がってしまいます。
さらに、超低金利のため、銀行預金だけではお金が増えず、気づかぬうちに資産を失っている状態です。
年間2%のインフレが続けば、現在100万円で買えるモノが、1年後には102万円なければ買えなくなります。
見方を変えれば、「100万円」の価値が、1年間で約2%下がったことを意味します。
インフレからお金を守るためには、資産運用でインフレ率以上のリターン(利益)を得て、資産を守らなければなりません。
現在の日本では、資産運用でお金を守り、お金に働いてもらう視点が必要です。
資産運用の成功は、リスク分散が鍵
資産運用で成功するためには、正しい知識を活用して、リスクを分散させるのがポイントです。
資産運用をはじめるにあたり、多くの初心者が「損をしたくない」「ギャンブルのようで怖い」という不安を抱きます。
多くの人が「投資=ギャンブル」と誤解する原因は、「投機」と「投資」の意味が混同しているためです。
投機とは、短期的な価格変動を狙って大きなリターンを得る方法を指し、非常にハイリスクです。
一方、投資は、長期的な視点で資産を保有し、資産が生み出す価値(企業の成長・配当・債券の利子など)を期待します。
投資はギャンブル要素のある投機とは違い、短期間で大きなリターンは得られませんが、リスクを分散させながら資産を増やせる方法です。
投資の世界には、「卵は一つのカゴに盛るな」という有名な言葉があります。
一つのカゴ(投資先)にすべての卵(資産)を入れ、カゴを落とした場合、すべての卵が割れてしまう可能性はゼロではありません。
しかし、複数のカゴに分けて盛っておけば、一つのカゴを落としても、他のカゴの卵は無事です。
これが「リスク分散」の基本的な考え方で、安全性の高い資産運用を目指したい人こそ、覚えておきましょう。
リスク分散には「長期・積立・分散」を押さえよう
資産運用のリスクを管理し、初心者が失敗を避けるための王道として知られているのが「長期・積立・分散」の三原則です。
長期:時間を味方につけよう
第一の原則は「長期投資」で、短期的な価格変動に一喜一憂せず、長い期間をかけて資産をじっくりと育てる方法を指します。
時間を味方につけることには、以下の大きなメリットがあります。
- 複利効果
複利とは、投資で得たリターンを元本に加えて再投資する方法を指し、お金がお金を生む流れを作れます。
アインシュタインが「人類最大の発明」と評価したほどで、運用期間が長ければ長いほど、雪だるま式に資産を増やす力として働きます。
- リターンの安定化
運用期間が長ければ長いほど、値動きは安定し、元本割れする可能性を低くできます。
一方、運用期間が短い場合、リターンがプラスにもマイナスにも大きく振れる傾向があるため、リスクは高めです。
一週間の間に価格が大きく変動しても、長期的に見れば小さな動きにすぎません。
長期投資を理解していれば、一時的な下落も冷静に運用を続けられるでしょう。
【おすすめの記事】
かしこくお金を増やす複利運用とは?効果を高めるポイントも解説
積立:買うタイミングを分散させよう
第二の原則は「積立投資」で、定期的に一定額の金融商品を買い続ける方法を指します。
「買うタイミング(時間)」を分散できるため、一括で投資するよりもリスクが低くなります。
「いつ買うか(売るか)」という判断は、プロの投資家にとっても難しい課題です。
初心者が「安いときに買って、高いときに売りたい」と考えても、タイミングを見極めるのは難しいでしょう。
しかし、積立投資は、価格が高いときには少なく、価格が安いときには多く購入できます。
結果として、平均単価が安くなり(ドルコスト平均法)、高値で購入するリスクを避ける効果を得られます。
感情に流されて損失をまねく売り方をしたり、投資を中断したりする危険を防ぎ、長期投資を継続するために必要です。
分散:投資先を分散させよう
第三の原則は「分散投資」で、「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉の通り、投資先を分散させるのも効果的です。
投資先(資産)を複数の対象に分けて投資すれば、さまざまなリスクから資産を守れます。
例えば、飲食の株式を3種類保有している場合、天候による不作や鳥インフルなどの問題が発生すれば、価格が下落します。
しかし、飲食・金融・通信の3種類に分けていれば、前述の問題が発生しても、2/3の株式には影響がありません。
他にも、株式・債券・不動産と資産を分散させたり、日本・アメリカ・インドと地域を分散させたりしましょう。
「分散」は、「長期」「積立」と並んで、リスク管理の重要な原則です。
資産運用で失敗しないための5つのポイント
三原則を正しく活用するためには、運用をはじめる前に押さえておくべき重要な「心構え」や「準備」があります。
①資産運用の目的・目標を明確にする
資産運用をはじめる前に「何のために」「いつまでに」「いくら必要か」という目的と目標を明確にしましょう。
目的によって、取るべきリスク(リスク許容度)や、選ぶべき運用商品、運用期間が異なるためです。
例えば、「30年後の老後資金として2,000万円」を準備する目的であれば、運用期間は30年も確保できます。
コツコツと資産を育てられる点が分かれば、ある程度のリスクを取ってリターンを狙う長期投資が可能です。
一方で、「3年後に使う子供の大学入学金として300万円」を準備する場合、運用期間は非常に短い点が分かります。
株式などのハイリスク商品は避け、貯蓄や元本が保障されている国債を購入するのもよいでしょう。
目的が曖昧なまま資産運用をはじめてしまうと、相性のよい手段を選べず、金融商品の価格が下落したときに不安になります。
目的と目標をしっかりと考え、資産運用の基盤を整えるのが重要です。
②リスク許容度を見極める
資産運用で成功するには、自身がどれほどの「リスク許容度」かを見極める必要があります。
リスク許容度とは、保有している金融商品の価格が下落したときに、経済的・精神的にどれほどの損失まで耐えられるかを示すラインです。
リスク許容度は、年齢・収入・資産状況・家族構成など、さまざまな要因によって異なります。
例えば、同じ独身でも、収入が安定している会社員と収入が不安定なフリーランスでは、取れるリスクの大きさは違うでしょう。
許容度を超えたリスクを取ってしまうと、相場が下落したときに判断を誤り、損失につながる可能性があります。
自身のリスク許容度を把握し、価格が下落しても冷静に対応できる基準を見つければ、資産運用で成功しやすくなります。
以下の記事では、リスク許容度の見極め方を紹介しているので、ぜひご覧ください。
▶関連記事:リスク許容度とは?資産運用で失敗しないために知るべき目安と決め方
③余裕資金の範囲で運用する
資産運用は、当面使う予定のない「余裕資金」でしましょう。
日々の生活費や、近い将来(数年以内)に使う予定が明確な(車や住宅の頭金・教育費など)お金を使うのはおすすめできません。
必要な資金を投資に回してしまうと、お金が必要なタイミングで相場が暴落していた場合、損失を確定させてしまいます。
また、「このお金が減ったら生活できない」というプレッシャーは、冷静な投資判断を妨げます。
精神的な安定を保ち、長期投資を継続するためにも、余裕資金の範囲内で資産運用をしましょう。
④「NISA」や「iDeCo」を活用する
資産運用をはじめる場合、お得に運用できる「NISA(ニーサ)」や「iDeCo(イデコ)」を活用しましょう。
これらの制度は、まさに「長期・積立・分散」投資を後押しするお得な制度です。
通常、株式や投資信託で得たリターン(売却益・配当・分配金)には、約20%の税金がかかります。
しかし、NISA口座内で投資して得たリターンには、税金がかかりません。
2024年からはじまった新NISAは、非課税保有期間が無期限化され、年間の投資枠も大幅に拡大するなど、資産形成の大切な基盤です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金準備に特化したさらに税制優遇が設けられています。
お得に運用できる制度を活用し、かしこく資産形成を進めましょう。
各制度の詳細は、以下の記事をご覧ください。
⑤金融リテラシーを高める
世界情勢の変化や保有資産の下落など、どのようなシーンでも冷静な資産運用を目指す人こそ、「金融リテラシー」を高めましょう。
金融リテラシーとは、お金の知識と判断力を指し、資産運用から保険の見直し、住宅ローンの選び方など、あらゆる問題を解決するスキルです。
これまで挙げた4つのポイント(目的・リスク許容度・余裕資金・NISAなど)を判断し、自分に合う手段を選ぶためには欠かせません。
金融リテラシーがあれば、銀行の窓口で進められた手数料の高い商品を選んでしまったり、不要な保険に加入するなどを回避できます。
他にも、株式の価格が下落した場合でも、「今が買い足すタイミングだ!」と判断し、資産を着実に増やしていけるでしょう。
知識は、金融機関や他人の意見を参考にしたうえで、自身で最適な判断を下すための「基盤」になります。
さらに、自身を守るための「リスク分散」にもつながるため、お金の知識を学習するのがおすすめです。
金融リテラシーは重要!FP資格で効率的に学ぼう
金融リテラシーを高めるには、6分野について学べるFP(ファイナンシャルプランナー)資格がおすすめです。
資産運用で役立つ!金融リテラシーの重要性
金融リテラシーは、資産運用の知識だけではありません。
社会保険・税金・住宅ローン・保険など、私たちが生きていく上で必要な知識を指します。
断片的な知識では、あらゆる問題に対応できず、本当に相性のよい手段を選べないでしょう。
例えば、本記事のテーマである「資産運用」は金融の知識だけでなく、税金や社会保険の知識が必要です。
知識がなければ、不要な税金を払ったり、受けられるはずの公的支援を見逃したりして、手元に残るお金を減らす可能性があります。
人生のあらゆる局面で「損をせず」「最適な選択」を選ぶための教養が、金融リテラシーです。
6分野を学べるFP資格が最適
体系的な金融リテラシーを、ゼロから網羅的に学びたい人には、FP資格がおすすめです。
FP資格の学習範囲は幅広く、以下の6つの分野に分かれています。
- ライフプランニングと資金計画:社会保険・年金・教育・住宅資金など
- リスク管理:生命保険・損害保険など
- 金融資産運用:投資信託・株式・債券・NISAなど
- タックスプランニング:所得税・住民税・年末調整・確定申告など
- 不動産:不動産売買・ローン・税金など
- 相続・事業承継:相続税・贈与税・遺言など
FP資格には、人生で必要となるお金の知識が詰まっています。
正しい知識を身につけた上で、自身や家族の状況に合わせた最適な「お金の答え」を自分で導き出す力を養いましょう。
資産運用で成功をつかむ!FPキャンプで学習を効率化
資産運用で成功をつかむ知識を本質から学べ、応用力と思考力を養えるのは、ほんださんが運営する「FPキャンプ」です。
本質から学べるから臨機応変な運用が可能
FPキャンプは、制度がある理由や背景、仕組みといった「本質」を丁寧に解説しています。
試験合格のために暗記した知識では、知識を実生活に当てはめられず、よい選択が難しいでしょう。
さらに、金融に関わる法律は、頻繁に改正されるため、暗記に頼った知識では柔軟に対応できません。
しかし、FPキャンプで「本質」を理解していれば、根底にある考え方を理解しているため、自身で応用し、臨機応変に対応できます。
本質的な理解こそが、試験合格後も変化し続ける環境の中で、長期的な資産運用を成功させるための「一生モノの知識」となります。
無料コースあり!有料コースは1か月約993円から
FPキャンプは、FP3級(学科試験)コースを無料で提供しています。
無期限・使い放題で試せるため、ほんださんの講義の分かりやすさや、学習システムの使いやすさを実際に体験できます。
また、有料プランは低価格に設定されており、経済的負担が気になる人でも安心して勉強を継続させられます。
FP3級(学科・実技試験)コースは、3か月間使い放題で2,980円(税込)で学べ、1か月に換算すると約993円です。
経済的ハードルを下げたFPキャンプで、質の高い授業を受けてみませんか。
【おすすめの記事】
【暗記量減】試験範囲が広いFP試験は「本質理解」で攻略!合格を勝ち取る勉強法
正しい知識でリスクを分散させよう
資産運用初心者が失敗のリスクを抑えるためには、「長期・積立・分散」が重要です。
さらに、目的の明確化、リスク許容度の把握、余裕資金での運用、NISAなどの活用、金融リテラシーを高めるのも成功ポイントです。
正しい知識を理解し、リスクを「怖いもの」から「管理・コントロールするもの」へと変化させましょう。
体系的なお金の学習には「FP資格」が適しており、より効率的に学びたい人には「FPキャンプ」がおすすめです。
資産運用を成功に導き、お金の不安を解決するための学びを、「FPキャンプ」の無料コースからはじめてみてはいかがでしょうか。