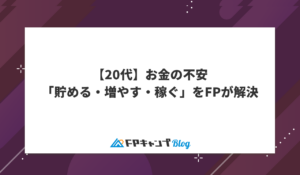24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
社会保険は、私たちの生活を守るために欠かせない、重要な制度です。
しかし、聞きなれない用語が多く、制度が複雑で「分かりにくい」と感じている人は多いでしょう。
社会保険は主に4つの保険で構成されており、働き方や年齢によって加入する制度や受けられる保障が異なります。
本記事では、社会保険について詳しく解説し、使いこなすために不可欠な「お金の知識」の重要性を紹介します。
将来の不安を解消し、自身や家族を守るための第一歩を踏み出しましょう。
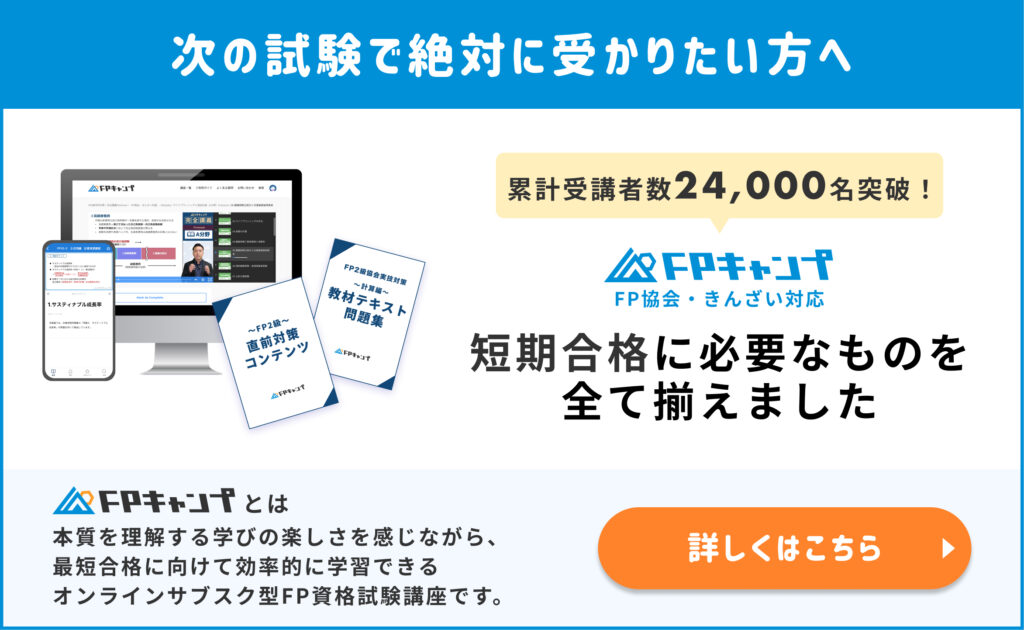
国民の生活を守る4つの社会保険
このセクションでは、①公的医療保険・②公的年金③介護保険・④雇用保険・労災保険(雇われている人)について解説します。
①公的医療保険
公的医療保険は、すべての国民が加入する義務があり、病気やケガで医療機関にかかったときの医療費負担を軽くします。
国民健康保険:自営業・フリーランス
国民健康保険(国保)は、自営業者・フリーランス・無職の人などが加入する医療保険です。
都道府県国保(都道府県・市町村)や国民健康保険組合が運営しており、後述の「健康保険」に該当しない人をカバーしています。
医療費の自己負担額は、以下のように年齢や所得で異なるため、注意しましょう。
| 一般・低所得者 | 現役並み所得者 | |
|---|---|---|
| 70歳~74歳 | 2割負担 | 3割負担 |
| 6歳~69歳 | 3割負担 | |
| 0歳~5歳 | 2割負担 | |
会社員とは異なり保険料の全額を自身で負担する必要があるため、しっかりと把握しておくのがおすすめです。
健康保険:会社員・公務員
健康保険(協会けんぽ・組合健保など)は、会社員や公務員、扶養家族が加入する医療保険です。
国民健康保険との大きな違いは、保険料の負担方法にあります。
健康保険の保険料は、会社と加入者本人が半分ずつ負担(労使折半)します。
保険料は給与(標準報酬月額)に応じて決まるため、給与が高いほど負担額は増える点を理解しておきましょう。
また、国民健康保険にはない手厚い給付が用意されている点も大きな特徴です。
以下の保障内容は、国民健康保険では得られません。
- 扶養制度
- 傷病手当:業務外の病気やケガで働けないときに支給される
- 出産手当金:出産時、仕事を休んだ期間に支給される
- 任意継続制度:退職した後でも、会社の健康保険に最大2年間加入可能
なお、自己負担額は国民健康保険と同じです。
75歳以降:後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上のすべての人が加入する医療制度です。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険から自動的に移行します。
ただし、一定の障害がある場合は、自身で申請することで65歳から加入できます。
(例)一定の障害に該当するもの
- 身体障害者手帳:1級~3級、4級の一部
- 障害年金:1級・2級
- 愛の手帳:1度・2度 など
自己負担額は、所得によって1割~3割と違いがあるため、注意してください。
| 割合 | |
|---|---|
| 現役並みの所得がある人 | 3割負担 |
| 一定の所得がある人 | 2割負担 |
| 一般的な所得の人 | 1割負担 |
②公的年金
公的年金は、働き方などによって加入する制度が異なり、一般的に「2階建て」の構造と呼ばれています。
国民年金(基礎年金)
国民年金(基礎年金)は、日本の公的年金制度の「1階部分」にあたります。
自営業者・フリーランス・会社員・公務員など、職業にかかわらず20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
なお、任意で60歳~65歳未満までは加入でき、将来のリスクに備えられます。
国民年金と聞くと、老後の生活を支える「老齢基礎年金」を想像する人が多いでしょう。
しかし、病気やケガで障害が残ったときの「障害基礎年金」、加入者が亡くなったときに遺族が受け取れる「遺族基礎年金」も受給できます。
原則として、保険料を納めた期間(免除期間なども含む)が10年以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受け取れる仕組みです。
未納のまま放置すると、これら3つの年金が受け取れないリスクもあるため注意が必要です。
保険料が支払えない状況のときは、保険料の免除や猶予制度を利用できるので、活用しましょう。
免除と猶予制度について知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
▶国民年金保険料の免除と猶予(ライフプランニングと資金計画)完全講義シリーズ
厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員が加入する公的年金で、国民年金(基礎年金)という「1階部分」に上乗せされる「2階部分」にあたります。
厚生年金に加入する人は、自動的に国民年金の加入者(第2号被保険者)にも該当します。
そのため、国民年金の内容に加えて、「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」が上乗せで保障される仕組みです。
保険料は給与や賞与の金額に応じて決まり、会社と折半(労使折半)で負担します。
将来受け取る老齢厚生年金の額は、加入期間の長さと給与にもとづいて計算されるため、老後の年金受給額は手厚くなる傾向にあります。
③介護保険
介護保険は、加齢に伴い介護が必要となったときに、少ない自己負担(原則1割~3割)で介護サービスを利用できます。
40歳以上のすべての人が加入対象となり、保険料を納める義務があります。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、特定の病気が原因で要介護状態となった場合にサービスを利用可能です。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、原因を問わず、要介護または要支援と認定されることでサービスを活用できます。
介護保険の詳細は、以下の記事をご覧ください。
▶公的介護保険(ライフプランニングと資金計画)完全講義シリーズ
④雇用保険・労災保険(雇われている人)
雇用保険と労災保険は、「雇われている人(労働者)」を対象とした制度で、自営業者やフリーランスの人は対象外です。
雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定、就職の促進を目的としています。
失業したときに受け取れる「失業手当」は、雇用保険をかけているからこそ受けられる給付金です。
ほかにも、育児休業中や介護休業中の生活を支える「育児休業給付金」「介護休業給付金」など、働く人を支援する制度です。
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中や通勤中に起きたケガ・病気・死亡などに対して保障します。
労災と認定されれば、治療費は全額支給され、休業中の所得補償(休業補償給付)も受けられます。
雇用保険と労災保険の詳細は、以下の記事をご覧ください。
正しく使いこなすには、お金の知識を学ぼう
社会保険制度を有効活用するためには、お金の知識が欠かせません。
社会保険制度は、幅広い保障を受けられるため、民間の保険に加入する前にしっかりと把握しておく必要があります。
一方、社会保険だけでは、すべてのリスクをカバーできないため、自身に必要な保険や手段は何かを選ぶために「お金の知識」が求められます。
例えば、公的年金が「いくらもらえるか」を知るだけでは不十分でしょう。
「老後に必要な生活費」から「年金受給額」を引き算し、不足する金額を「いつまでに」「どうやって準備するか」を考えなければなりません。
自身の貯蓄額・働き方・家族構成など踏まえ、どれくらいの自己負担なら耐えられるかを判断する知識が求められます。
公的保障を土台として活用しつつ、足りない部分を自分で補う金融リテラシーこそが、将来の不安から自身と家族を守るでしょう。
効率的に勉強するなら「FP資格」がおすすめ
社会保険を含むお金の知識を、効率的に学びたい人には、ファイナンシャルプランナー(FP)資格の学習がおすすめです。
FP資格の学習範囲は、人生において切り離せないお金の6分野を網羅しています。
- ライフプランニングと資金計画(社会保険・年金・住宅ローンなど)
- リスク管理(生命保険・損害保険・公的医療保険など)
- 金融資産運用(NISA・iDeCo・株式・投資信託など)
- タックスプランニング(所得税・住民税・各種控除など)
- 不動産(不動産売買・税金・法律など)
- 相続・事業承継(相続税・贈与税・遺言など)
本記事で解説した社会保険は、主に「1. ライフプランニングと資金計画」に含まれます。
FPの学習を進めると、社会保険の知識が、税金(タックス)・資産運用(金融)・保険(リスク)との関係を理解できます。
関係性を理解しているからこそ、自身の状況に合わせた選択が可能になり、資産を守り、増やすことにつなげられるでしょう。
例えば、老後資金に対して漠然とした悩みがある場合、FPの知識があれば、以下の知識を組み合わせた具体的な解決策を考えられます。
- 公的年金(ライフプランニングと資金計画)
- NISA・iDeCo(金融資産運用・タックスプランニング)
- 生命保険(リスク管理)
- 退職金(タックスプランニング)
お金の知識を断片的に集めるのではなく、人生全体で役立つ「実践的なスキル」として身につけるのが、経済と心の安心につながるといえます。
FP試験の合格と「応用力」を学ぶならFPキャンプ
FP資格の学習を通じて、試験合格と本質的なお金の知識まで勉強したい人には、「FPキャンプ」が最適です。
本質を知れるから、応用力が身につく
FPキャンプは、試験テクニックや丸暗記に頼らず、知識の「本質」から理解できるため、生きた知識を身につけられます。
「なぜこの制度が存在するのか」「どのような仕組みで成り立っているのか」という根本を、ユーモアを交えて分かりやすく解説します。
実生活で起きるお金の課題に対しても、学んだ知識を応用して「自分で考える力」が得られ、より豊かな環境を作れるでしょう。
法改正や経済の変化に対応できる応用力を身につけたい人こそ、FPキャンプを活用してみてください。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
無料プランを用意!思った瞬間からはじめられる
FPキャンプは、学習をはじめやすいように「無料プラン(FP3級学科試験対策コース)」を用意しています。
「自分に合うか分からない」「続けられるか不安」などの理由で、勉強を諦める必要はありません。
無期限でじっくりと試せるため、学習をはじめるときの心理的、経済的なハードルを大幅に下げてくれるでしょう。
「学びたい」と思ったその瞬間から、すぐにFPの勉強をはじめられる学習コンテンツこそが、FPキャンプです。
【おすすめの記事】
【朗報】FP3級の独学が変わる!FPキャンプなら学科試験対策が無料で使い放題に
有料プランは低価格!サブスク制で経済的負担を減らす
さらに本格的に学べる有料プランは、1か月約993円からとお手頃価格で提供しています。
学科試験と実技試験を学べるFP3級コースは、3か月間使い放題で2,980円(税込)で利用可能です。
一般的な資格スクールのような高額な一括払いの受講料ではなく、低価格なサブスクリプション制を採用しています。
忙しい社会人や主婦(主夫)でも勉強を続けられるよう、使う期間のみ料金が発生するので安心です。
低価格ながらも、高品質な講義動画や充実したアウトプット教材をすべて利用できるコストパフォーマンスのよさを、ぜひ体感してください。
お金の知識で自身や家族を守ろう
社会保険は、国民の生活を守るための優れた制度です。
公的医療保険・公的年金・介護保険・雇用/労災保険は、どの保険も人生の重要な局面で私たちを支えてくれます。
しかし、制度は複雑で、公的保障だけですべてをカバーできません。
医療費の自己負担、老後資金の準備、介護への備えなど、「自助努力」が大切な時代へと変化しました。
この時代をかしこく生き抜くために必要なのが、幅広いお金の知識です。
FPの学習を通じてお金の知識を身につけ、将来に対する漠然とした不安を「具体的な安心」に変化させましょう。
お金の知識は、これからの時代を生き抜くための「武器」として、自身と大切な家族を守る「盾」として役立ちます。
FPキャンプでの本質的な学びを通じて、「守る力」を手に入れてはいかがでしょうか。