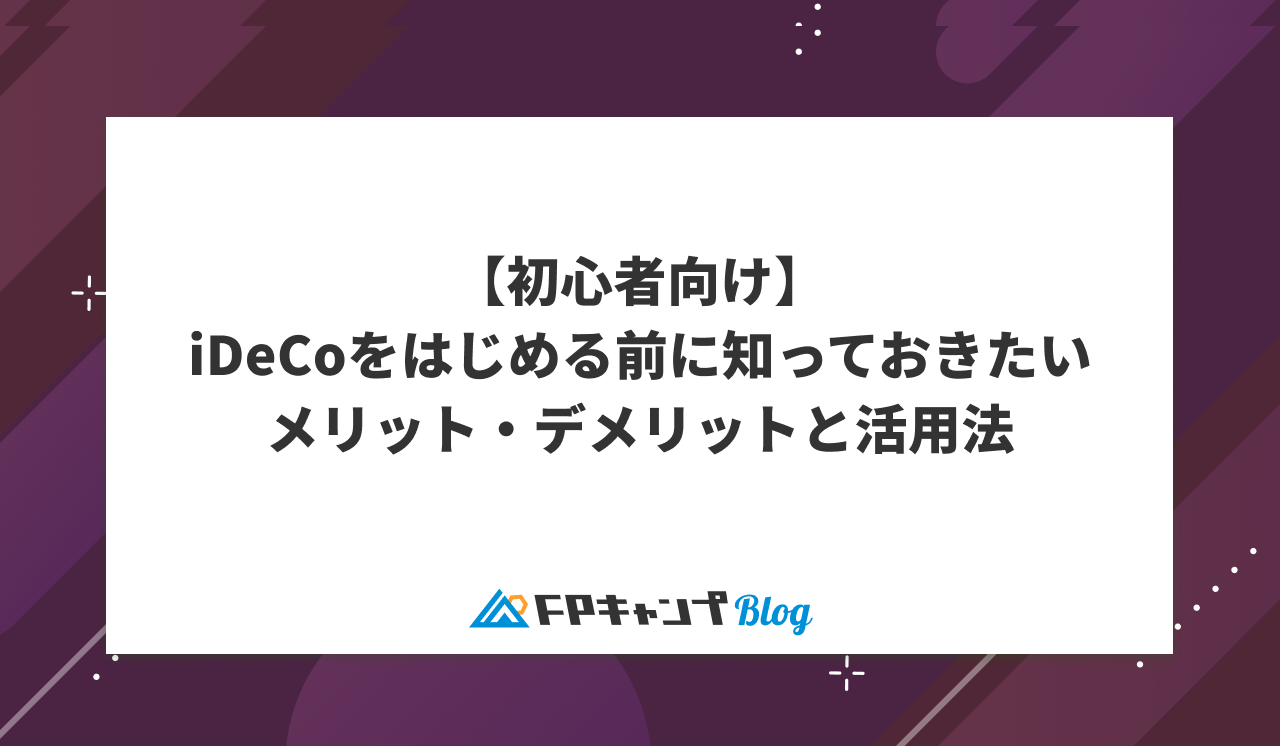24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
将来の老後資金に不安を感じ、「何からはじめたらいいのだろう」と思っている人もいるでしょう。
老後資金対策には、iDeCo(イデコ)が向いており、税金面で得をしながら資産形成ができます。
ただし、メリットだけでなくデメリットも存在するため、iDeCoについて知り、慎重に決断する必要があります。
仕組みを正しく理解しないままはじめてしまうと、本来得られるはずの利益を逃してしまうかもしれません。
本記事では、iDeCoの基本的な仕組みから、メリット・デメリット、活用法まで、FPの目線で分かりやすく解説します。
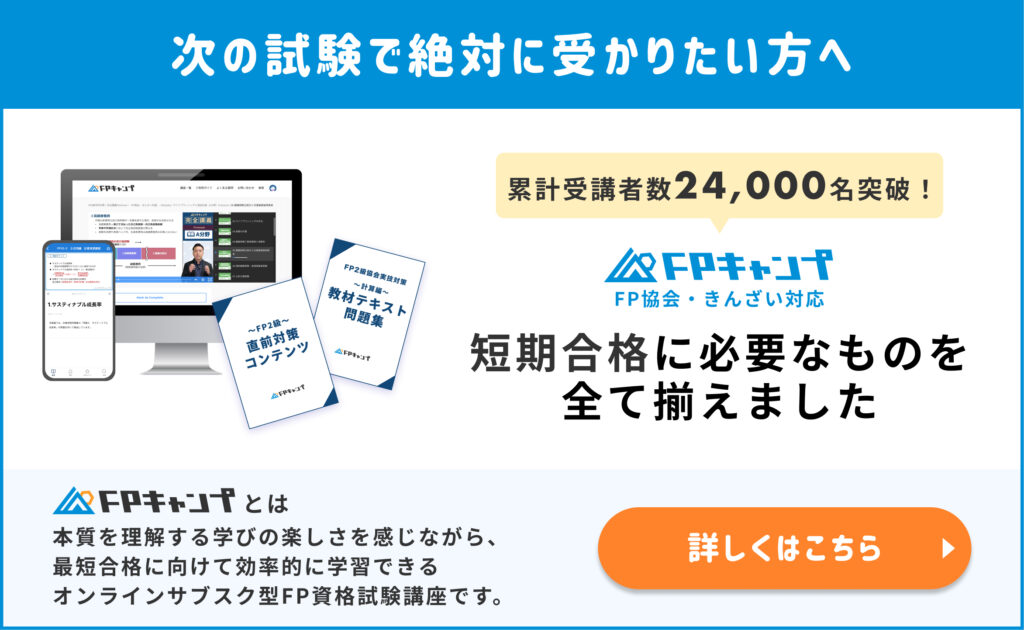
iDeCoとは?老後資金準備におすすめの制度
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、将来に備えて自身で掛金を積み立て、自身で選んだ金融商品で運用する私的年金制度です。
公的年金の国民年金や厚生年金に加え、任意で上乗せできる仕組みと考えると分かりやすいでしょう。
iDeCoが老後資金準備におすすめされる理由に、国が用意した手厚い税制優遇措置を受けながら資産形成ができる点が挙げられます。
公的年金だけではゆとりある老後生活が難しいといわれる現代において、iDeCoは将来のためのよい選択肢といえます。
FP目線で解説!iDeCoのメリット・デメリットとは?
iDeCoをかしこく活用するためには、メリットとデメリットの両面を正しく理解し、自身に適しているか見極めましょう。
iDeCoの3つのメリット
iDeCoのメリットは、「拠出時」「運用時」「受取時」の3つの段階すべてで、手厚い税制優遇が受けられる点です。
①拠出時:掛金が全額所得控除になり、税金が安くなる
iDeCoの掛金は、全額が「所得控除」の対象となるため、節税効果を発揮します。
所得控除とは、税金の計算対象となる所得金額(課税所得)から、所得控除分の金額を差し引ける仕組みです。
税金の対象となる所得金額が減るため、納める所得税と翌年に納める住民税の負担が軽減されます。
例えば、年収500万円の会社員が、毎月2万円を65歳になるまで運用した場合、税金負担の変化は以下の通りです。
積立時
| iDeCoを利用する | iDeCoを利用しない | |
|---|---|---|
| 所得税額 | 11万4,550円 | 13万8,550円 |
| 住民税額 | 21万7,050円 | 24万1,050円 |
この場合、年間の節税額は4万8,000円、35年間の節税額は168万円と大きな節税につながります。
iDeCoを活用すれば、お得に資産形成を進められるため、漠然としたお金の不安を安心に変えられるでしょう。
②運用時:運用で得た利益(運用益)がすべて非課税になる
通常、投資信託などの金融商品で得られた利益(分配金や売却益)には、20.315%の税金がかかります。
内訳は、以下の通りです。
しかし、iDeCoの口座内で運用して得たリターン(利益)は、20.315%の税金がかかりません。
例えば、投資で10万円のリターンが出たとします。
通常の課税口座であれば、約2万円が税金として差し引かれ、手元に残るのは約8万円です。
一方、iDeCoの口座であれば10万円を受け取れ、そのまま再投資に回せます。
iDeCoの非課税のメリットは、長期運用で力を発揮する「複利効果」をさらに活かせます。
複利とは、運用で得たリターンを使うのではなく、掛金と一緒に運用する方法です。
掛金の合計額(元本)が増えるので、お金がお金を生む流れを作れ、よりスピーディーに資産を増やせます。
この複利運用に対して、アインシュタインは「人類最大の発明」と呼ぶほど、投資を成功させる上で重要な運用方法です。
iDeCoは長期的な資産形成において、非常に効率的な制度設計だといえるでしょう。
③受取時:受け取る際も大きな控除が適用される
iDeCoで積み立てたお金を受け取る「出口」の段階でも、大きな税制優遇が用意されているのがiDeCoのメリットです。
受け取り方は、「一時金」として一括で受け取る方法と、「年金」として分割で受け取る方法の2種類があり、控除が適用されます。
一時金で受け取る場合は、「退職所得控除」が適用されるため、多くのお金を手元に残せます。
これは、iDeCoの加入期間(勤続年数とみなされる)に応じて、非課税枠が大きくなる仕組みです。
【退職所得控除】
勤続年数(iDeCo加入期間)20年未満:40万円 × 勤続年数
勤続年数(iDeCo加入期間)20年以上:800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 – 20年 )
つまり、iDeCoを25年間運用していた場合、1,150万円もの金額を控除できます。
年金形式で受け取る場合は、「公的年金等控除」が適用されます。
公的年金等控除が適用されれば、国民年金や厚生年金と合算しても、一定額までは税金がかかりません。
公的に年金に係る雑所得以外の合計所得が1,000万円以下のケース
| 公的年金等の年間収入金額 | 計算式 | |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超 130万円未満 | 年金収入額 – 60万円 | |
| 130万円以上 410万円未満 | 年金収入額 × 0.75 – 27万5,000円 | |
| 410万円以上 770万円未満 | 年金収入額 × 0.85 – 68万5,000円 | |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 年金収入額 × 0.95 – 145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 年金収入額 – 195万5,000円 | |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超 330万円未満 | 年金収入額 – 110万円 | |
| 330万円以上 410万円未満 | 年金収入額 × 0.75 – 27万5,000円 | |
| 410万円以上 770万円未満 | 年金収入額 × 0.85 – 68万5,000円 | |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 年金収入額 × 0.95 – 145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 年金収入額 – 195万5,000円 |
このように、資産を積み立てる入口から、最終的に受け取る出口まで、税制メリットを享受できる制度がiDeCoです。
iDeCoの3つのデメリット
大きなメリットがある一方で、iDeCoには注意すべきデメリットも存在します。
①原則60歳までお金を引き出せない
iDeCoは老後資金の準備を目的としているため、積み立てた資産は原則として60歳になるまで引き出せません。
この、お金の動かしやすさ(流動性)が低い点は、iDeCoで注意すべきデメリットです。
例えば、住宅購入の頭金や子供の教育費など、60歳より前に大きな資金が必要になったとしても、iDeCoの資産をそれに充てることはできません。
そのため、iDeCoに拠出する掛金は、あくまで日々の生活に影響のない「余裕資金」の範囲で設定する必要があります。
ただし、途中で家計が苦しくなった場合などには、掛金の金額を年に1回のみ変更できたり、一時的に停止したりできます。
引き出しはできなくても、拠出を柔軟に調整できることは覚えておくとよいでしょう。
iDeCoの流動性の低さを理解した上で、老後資金の準備を進めるのがおすすめです。
②損する可能性がある
iDeCoで選択できる商品には、定期預金や保険といった「元本確保型」と、損失する可能性のある投資信託「元本変動型」があります。
元本変動型は、投資に該当するため、市場の変動によって資産価値が上下します。
運用がうまくいかなかった場合、積み立てた掛金の合計額を下回る「元本割れ」のリスクがあるので注意しましょう。
しかし、元本割れのリスクは「長期・積立・分散」という投資の基本原則を実践すれば、リスクを軽減できます。
時間をかけてコツコツと積み立て、さまざまな資産に分散投資されている商品を選び、長期的なリターンを目指してください。
③手数料がかかる
iDeCoに加入して運用するには、いくつかの手数料が必要です。
手数料は大きく分けて、加入時(乗り換え時)にかかるものと、運用中に継続してかかるものの2種類があります。
詳細は、以下をご覧ください。
- 加入時
国民年金基金連合会に支払う手数料:2,829円
- 運用中
国民年金基金連合会と信託銀行に支払う手数料:合計 月額171円
金融機関(運営管理機関)に支払う運営管理手数料:金融機関によって異なる
これらの手数料がかかる点を考慮し、iDeCoをはじめましょう。
iDeCoのメリットを活かすポイント
iDeCoの強力な税制優遇メリットを引き出すためには、どの金融商品で運用するかという「商品選び」が重要な鍵を握ります。
金融機関選びは慎重に
商品選びは、iDeCoに加入する金融機関(運営管理機関)を選んだ時点からはじまっています。
金融機関によって、運用できる商品のラインナップや、先述した運営管理手数料が大きく異なるためです。
手数料が高い金融機関を選んでしまうと、それだけで手元に残る金額が減るため、慎重に選びましょう。
運営管理手数料が低く、低コストで優良な投資信託を数多くそろえている金融機関を候補にするのが、かしこいiDeCoのはじめ方といえます。
信託報酬を比較する
投資信託で運用をする場合、重要視すべき指標が「信託報酬」です。
信託報酬とは、投資信託を保有している間、支払い続けるコスト(手数料)を指し、金額は金融機関によって異なります。
信託報酬は、運用成果に関わらず、信託財産から毎日差し引かれるため、低コストの商品を選ぶようにしましょう。
商品を理解する
運用する商品のリスクとリターンの関係性をしっかりと理解する必要があります。
例えば、投資信託で運用する場合、以下の投資対象によって特徴が異なります。
- 全世界株式
先進国や新興国など、世界中の企業の株式に広く分散投資します。これだけで世界経済の成長の恩恵を受けられ、国によるリスク分散も可能です。
- 米国株式
S&P500など、アメリカの主要企業の株式に投資します。投資家から人気の指数も多く、今後も高いリターンが期待されています。
- バランス型
株式だけでなく、値動きが比較的安定している債券なども組み合わせて、リスクを抑えた運用を目指します。
自身がどの程度のリスクを受け入れ、どの程度のリターンを期待するかによって選択は変わるため、慎重に選びましょう。
リスク許容度の確認
自身のリスク許容度(どの程度の損失を受け入れられるか)が、どれくらいか見極めましょう。
リスク許容度は、年齢・収入・資産状況・投資経験・性格など、人によって異なります。
例えば、20代や30代の人は、60歳まで運用できる期間が長いため、短期的な価格変動があっても時間をかけて回復を待てます。
そのため、リスクは高いものの大きなリターンが期待できる、株式中心の商品を選ぶという選択もよいでしょう。
一方で、60歳に近い50代の人は、運用期間が短いため、大きな価格変動は避けたいと考えるのが一般的です。
その場合、債券の比率が高いバランス型の商品などで、安定的な運用を心がけるのも1つの選択でしょう。
自身の状況を客観的に見つめ、どの程度のリスクなら受け入れられるかを考えてみてください。
【結論】iDeCoの不安は「FPの知識」で解消できる
iDeCoの商品選びに関する4つのポイントを解説しましたが、iDeCoをフル活用するためには、お金の知識を学ぶのが最適です。
金融機関を選び、信託報酬を比較し、商品の内容を理解した上で、自身のリスク許容度を確認するには、基盤となる知識が必要です。
FPが持つ、幅広いお金の知識を身につければ、不安を安心に変えられるでしょう。
表面的な情報だけでなく、その背景にある経済の仕組みや投資の理論を学べば、iDeCo以外のお金の問題もまとめて解決できます。
FPの学習なら、FPキャンプで効率的に学ぶ
iDeCoを含む、お金の問題を解決したい人には、本質から学べる「FPキャンプ」がおすすめです。
魅力①:経済変化に動じない力が身につく
FPキャンプでの学習は、単なる資格取得にとどまらない、一生使える金融リテラシーが身につきます。
経済は常に変化しており、将来どのような金融商品が登場し、どのような経済状況になるかは誰にも予測できません。
FPの学習を通して、金利・為替・インフレ・法改正などで揺れ動く経済変化に動じない、判断力を養えます。
iDeCoの商品選びだけでなく、将来の経済ニュースを正しく読み解き、自身の資産を守り育てていくための力が身につくでしょう。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
魅力②:無料プランあり!有料プランもお手軽価格
FPキャンプは、FP3級の学科試験が無料で学べるため、勉強したいと思った瞬間から学習をはじめられます。
どのような内容を学べるのか、自分に合っているかを確かめてからはじめられるため、勉強へのハードルを低くできます。
さらに、FP3級の学科・実技試験が学べるコースは、3か月間使い放題で2,980円(税込)とお手頃価格で学習可能です。
スマホやPCがあれば、いつでもどこでも学習できるため、忙しい社会人でもスキマ時間を有効活用して学べるでしょう。
【おすすめの記事】
【朗報】FP3級の独学が変わる!FPキャンプなら学科試験対策が無料で使い放題に
iDeCoはお金の知識で解決!不安を安心に変えよう
iDeCoは、税制優遇という国の強力な後押しを受けながら老後資金を準備できる優れた制度です。
しかし、恩恵を引き出すためには、金融機関や商品を自身で選び抜く力が求められます。
将来、iDeCoを含むさまざまなお金の問題で後悔したくない人にこそ、お金の知識が重要です。
将来のお金に対する漠然とした不安は、お金の知識があれば、具体的な安心へと変えられます。
iDeCoへの加入をきっかけに、FPキャンプのような場で専門知識を学び、資産形成の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい!FP資格の詳細はこちら
FP資格の詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
【FPとして働く】