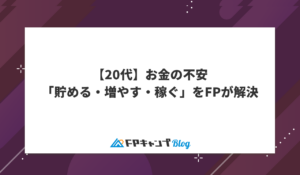24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
新NISAやiDeCoなどのキーワードを耳にする機会が増え「投資の勉強をはじめたい」と考える人は増えています。
しかし、情報が多すぎて何から手をつければよいか分からず、はじめの一歩を踏み出せない人も少なくありません。
遠回りをせず、着実に投資の知識を身につける最短ルートは、ファイナンシャルプランナー(FP)資格の学習です。
FPの学習は、投資の知識だけでなく、税金や社会保険などの幅広い知識を学べるため、資産形成に必要な土台を築けるでしょう。
本記事では、FPがお金の勉強をせずに投資をはじめる危険性や、FP資格が投資の勉強に最適な理由まで解説します。
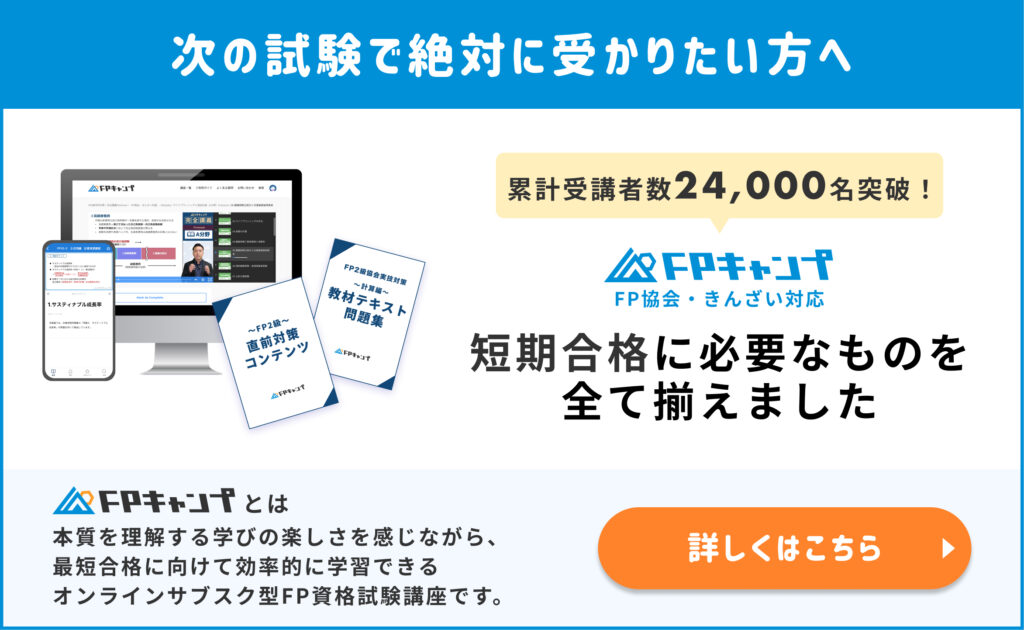
【注意】お金の勉強をしないで投資をはじめる4つの危険
お金の知識がないまま投資をはじめる場合、大きく分けて4つの危険が潜んでいます。
危険①:リスク許容度にあった資産運用ができない
お金の知識がないまま投資をはじめると、自身の「リスク許容度」に合わない資産運用をしてしまう危険性があります。
リスク許容度とは、自身がどれくらいの損失に精神的・経済的に耐えられるかの度合いを指し、投資において重要なポイントです。
リスク許容度を知らないまま投資をはじめてしまうと、予想以上の損失が生じてしまい、生活に支障が出てしまうでしょう。
例えば、収入が多くなく、養うべき家族がいる人が投資を知識のないままはじめてしまうと、不安で夜も眠れなくなるかもしれません。
最近では、株主優待を受けたいという理由から、お金の知識がないまま株式投資をはじめてしまい、値動きに一喜一憂する人も増えています。
正しい知識がない場合、少しの値下がりでも冷静な判断ができなくなり、大きな失敗につながる可能性もあるでしょう。
FPの学習では、自身の収入・支出・資産状況や、投資との向き合い方、適切なリスク許容度を把握するプロセスを学びます。
自身の器の大きさを把握すれば、失敗しない資産運用の第一歩になるため、FPの勉強は欠かせません。
危険②:値動きに振り回され、誤った判断をしてしまう
投資の目的や金融商品の特徴を理解していないと、日々の価格変動に振り回され、感情的な判断を下してしまいやすい傾向にあります。
例えば、株価が暴落したときに恐怖心から売却してしまう「狼狽売り(ろうばいうり)」は、よい判断ではない場合も少なくありません。
2019年末に発生した新型コロナウイルスが引き起こした「コロナショック」で、日経平均株価は3割減となりました。
2020年3月19日の日経平均株価は1万6,553円まで下落しましたが、2025年9月22日時点では4万5,493円まで上昇しています。
企業の成績不振や自身のリスク許容度に合わない場合は、売却する方がよいケースもありますが、見極めが重要です。
正しい判断ができれば、「株価の下落は金融商品を安く買えるチャンス」と捉え、投資を前向きに楽しめるでしょう。
感情に流されないためにも、過去のデータや金融商品の特性といった客観的な知識は、投資をする上で不可欠です。
危険③:お得な制度を活用できない
現在の日本では、NISAやiDeCoといった、個人の資産形成を税制面で優遇するお得な制度が用意されています。
これらの制度を活用すれば、通常は投資のリターンに対して約20%かかる税金が非課税になります。
知識がなければ制度の恩恵を十分に受けられず、大きな機会損失につながるため、お金の知識は重要です。
例えば、年間30万円のリターンが出た場合を考えてみましょう。
通常の課税口座であれば約6万円(30万円×20.315%)の税金が引かれますが、NISA口座であれば税金は0です。
教育資金や老後資金のために投資をする場合、リターンは非常に大きくなり、活用しないのは非常にもったいないでしょう。
さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)には、掛金が全額所得控除になるというメリットもあります。
年収500万円の会社員が毎月2万円をiDeCoに拠出した場合、所得税と住民税を合わせて年間4万8,000円もの節税が可能です。
知らないだけで損をしてしまうのが、資産運用の世界だといえるでしょう。
危険④:手数料の高い商品や投資詐欺に遭う確率が高まる
金融リテラシーが低いと、金融機関の窓口や営業担当者に勧められるがまま、手数料の高い商品を購入してしまう可能性があります。
金融機関の商品が悪いという訳ではありませんが、手数料が高く設定されているケースが多いため、あらかじめ理解しておく必要があります。
例えば、以下の投資信託を比較してみましょう。
- 元本:1,000万円
- 運用期間:10年
- A商品:購入手数料3%、信託報酬2%
- B商品:購入手数料0%、信託報酬0.1%
- 利回りは考慮せず、手数料だけで単純計算
この場合、A商品とB商品の手取り額は、以下のような差がでます。
- A商品の計算
購入手数料:1,000万円×3%=30万円→投資額 970万円
信託報酬(運用中手数料2%×10年×元本の簡易計算):970万円×2%×10年=194万円
手取り額:970万円−194万円=776万円
- B商品の計算
購入手数料:0円
信託報酬:1,000万円×0.1%×10年=10万円
手取り額:1,000万円−10万円=990万円
- A商品とB商品の差額
B商品の方が214万円多く受け取れる
このように、手数料の差で受け取れる金額が異なるため、正しい知識をもとにしっかりと見極めなければなりません。
また、「絶対に儲かる投資」などの勧誘をする投資詐欺の被害に遭うリスクも軽減できます。
正しい知識があれば、「投資の世界に絶対はない」と詐欺を見抜く防衛力を身につけられるでしょう。
大切な資産を守るためにも、金融商品の特徴を学ぶ必要があります。
FP資格が投資の勉強におすすめな3つの理由
お金の知識を効率よく、網羅的に学ぶ上でFP資格の学習が最適です。
理由①:自分だけの「投資軸」を作れるため
FPの学習は、自分だけの「投資軸」を作るのに役立ちます。
SNSやネットでは「〇〇がおすすめ」「今買うべき銘柄」などの情報が溢れていますが、これらはすべての人に最適な商品とは限りません。
FPの学習を通じて、自身のライフプランやリスク許容度を明確にすれば、他人の意見に流されなくなるでしょう。
投資軸があるからこそ、市場が好調なときも過度に楽観せず、市場が暴落したときでも冷静な判断を下せるようになります。
理由②:お金に関する知識を幅広く学べるため
FP資格の魅力は、お金に関する6つの分野を「体系的」に学べる点です。
体系的に学ぶとは、物事を個別のパーツとしてではなく、全体のつながりを意識して学ぶことを指します。
例えば、「家を買うか、賃貸に住み続けるか」で悩んでいる場合、人生を左右する高額な買い物でもあるため、正しい判断が重要です。
断片的な知識しかないと、「住宅ローン控除がお得だから買うべき」「固定資産税が大変だから賃貸がよい」など目先の情報に振り回されがちです。
しかし、FPの知識があれば、「本当に持ち家が必要か」を客観的に考えられ、保険・投資・税金・相続の観点から総合的に判断できます。
このように、お金の知識の全体像を捉えることで、より最適な判断を下す力が身につくでしょう。
理由③:NISAやiDeCoなど「勝つための制度」を理解できるため
FPの学習を通じて、NISAやiDeCoを学べば、資産形成を有利に進められます。
「非課税になるらしい」という表面的な知識だけでなく、学習を通じて本質的な部分を理解できれば、より効果的に活用可能です。
例えば、iDeCoには掛金の所得控除、運用益の非課税、受取時の控除という3つの税制優遇があります。
知識があれば、どのタイミングで、どの程度のメリットがあるのかを自身の状況に合わせて考えられるでしょう。
制度の本質を理解するからこそ、自身のライフプランや収入に合わせて最適な活用法を見つけ出し、資産を着実に増やせます。
FP資格を投資にどう活かす?実践例を紹介
FPで学ぶ知識がどう投資で活かせるのかについて、投資と関連の深い3つの分野を例に挙げて紹介します。
ライフプランニング:投資の「目的」と「ゴール」を明確化
ライフプランニングとは、結婚・出産・住宅購入・老後など、人生のさまざまなイベントを見据え、実現可能な資金計画を立てるプロセスです。
ライフプランニングの知識は、投資をする目的を達成する上で不可欠といえます。
投資は、大切な資産が関わるため、「なんとなくはじめる」「周りがしているから」といった理由でするのはおすすめできません。
「何のために、いつまでに、いくら必要なのか」を明確にするからこそ、相性のよい金融商品、運用期間や投資金額という戦略が立てられます。
また、FPの学習では、「キャッシュフロー表」という家計の収支予測表の作成方法も学びます。
キャッシュフロー表を作成できれば、将来の資金不足の時期や、余裕のある時期を可視化でき、より現実的に動けるでしょう。
金融資産運用:NISAや個別株選びの普遍的な基礎を学ぶ
「金融資産運用」の分野では、投資で必要な知識を学びます。
株式・債券・投資信託などの各金融商品の特徴や、リスクとリターンの関係、経済指標の読み解き方など、網羅的に学習可能です。
また、リスクを軽減するための「分散投資」「積立投資」「長期投資」の重要性も深く学びます。
投資には必ずリスクがつきまとうため、リスクとうまく付き合う方法を学ぶことで、より安全性を求めた資産形成が可能です。
これらの基礎知識があれば、NISAで投資信託を選ぶ際に、商品の特徴やコストを自身で比較検討できるようになるでしょう
流行りの銘柄に飛びつくのではなく、自身の判断基準で金融商品を選び抜く力が養われます。
タックスプランニング:税金を味方につけ、手取り額を上げる
タックスプランニングとは、税金の仕組みを理解し、法律に則った形で納税額を抑えるための計画を立てる考える知識です。
投資で得たリターンを多く手元に残すためには、税金の知識が欠かせません。
NISAやiDeCoの活用や、投資で損失が出た場合に他のリターンと相殺して税金の負担を軽減する「損益通算」などの重要な知識です。
例えば、ある年にA株で50万円のリターン、B株で20万円の損失が出たとします。
損益通算をすれば、リターンは30万円(50万-20万)とみなされ、課税対象になる金額が減らせ、節税可能です。
これらの知識を知っているか知らないかで、最終的に手元に残る金額は大きく変わってきます。
投資の勉強はFP何級から?レベル別のロードマップ
FP資格で投資の勉強をはじめる人に向けて、レベル別にFP資格の等級を紹介します。
まずはFP3級がおすすめ!お金の全体像を把握しよう
投資初心者や、これまでお金の勉強を本格的にしてこなかった人は、まずFP3級の取得を目指すとよいでしょう。
FP3級は、お金に関する6分野の基礎知識を幅広く学べる入門資格であり、資産形成の全体像をつかむのに適しています。
投資に大きく関わる分野の「金融資産運用」だけでなく、税金・年金・保険などの分野の基本を学ぶのがおすすめです。
合格率も比較的高いため、学習の成果が成功体験となり、次のステップへ進むモチベーションにもなるでしょう。
まずはFP3級の学習をはじめ、金融リテラシーの土台を固めて、人生を豊かにする投資について学んでみてください。
【おすすめの記事】
「FP3級は意味ない」は本当?取るべき人や不要な人、メリット・注意点をFPが解説
本格的な資産運用を目指すならFP2級が最適解
FP3級で得た基礎知識を土台に、より本格的な資産運用を実践していきたいと考えるなら、FP2級の取得が最適解といえるでしょう。
FP2級は、金融機関の実務でも求められる専門的な知識を問われる等級です。
FP3級よりも一歩踏み込み、個人の資産状況に応じた「ポートフォリオ」の考え方を学びます。
ポートフォリオとは、保有する金融商品の組み合わせや割合を指し、理想のリターンやリスク許容度によって変化します。
投資信託だけでなく、株式・債券・仮想通貨などをより本格的に運用したい人にとって、役立つ知識です。
FP2級まで学習すれば、自身で経済ニュースを読み解き、投資判断に活かす応用力も身につきます。
自信を持って自身の資産ポートフォリオを構築し、リスクを管理しながら、より積極的に資産を増やす戦略を立てられるでしょう。
【おすすめの記事】
ファイナンシャルプランナー試験はいきなり2級から挑戦できる?受験資格や難易度を解説
効率的に学ぶならFPキャンプ!投資に活きる3つの魅力
最短で投資に使える「本質的な知識」を身につけたい人には、ほんださんが運営する「FPキャンプ」がおすすめです。
魅力①:投資で本当に使える本質的な知識が身につく
FPキャンプでは、「本質理解」を重視した授業をしているため、自身の状況に合わせた資産運用を可能にします。
暗記で得た知識の場合、現状に知識を当てはめられず、知識を活用できないケースも少なくありません。
しかし、FPキャンプでは、制度ができた背景や目的から丁寧に解説するため、知識が深く記憶に定着し、応用力が身につきます。
法改正や新しい金融商品に柔軟に対応するためにも、本質から理解するのがおすすめです。
FPキャンプで学ぶ「なぜそうなっているのか」という本質的な知識は、変化の激しい時代を生き抜くための、本物の武器となります。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
魅力②:1か月約993円!書籍1冊より安く始められる手軽さ
FPキャンプは、質の高い講義を嬉しい低価格で受講できる点も大きな魅力です。
FP3級対策は、3か月使い放題で2,980円(税込)と低価格に設定されており、気軽に学習をはじめられます。
FPキャンプの価格設定は、学びたいという気持ちを行動に移すハードルを大きく下げ、多くの人にとっての力強い味方になるでしょう。
驚きの価格で、FPの勉強に必要なテキスト・問題集・講義動画が揃うので、ぜひ活用してみてください。

コース別の詳しい料金は、FPキャンプの公式サイトをチェック!
魅力③:多数の合格者の声が証明する、講義の質の高さ
FPキャンプの学習コンテンツは、低価格さと質の高さを両立しています。
どれだけ価格が安くても、質が伴わなければ意味がありません。
しかし、FPキャンプは、多くの受講生を合格へと導いてきた豊富な実績が、質の高さを証明しています。
FP解説で人気のほんださんによる、複雑な内容もかみ砕いて説明する分かりやすい講義は、勉強が苦手な人にもおすすめです。
信頼できる教材で、着実に知識を身につけたい人にこそ、最適な学習コンテンツでしょう。
あわせて読みたい!FP資格の関連記事
FP資格の関連記事を紹介するので、FP資格の本当の価値を活かすためにも、ぜひ参考にしてください。
▶FP資格とは?:ファイナンシャルプランナー(FP)とは?メリット・勉強方法を徹底解説
▶FP資格の試験日:2025年版|ファイナンシャルプランナー(FP)試験日まとめ!申込期間・受験料なども解説
▶実施団体の選び方:FP|日本FP協会ときんざいどっちを選ぶべき?違い・選び方・難易度の低さを徹底解説
▶効率的な学習テクニック:【FP試験対策】もう勉強方法に迷わない!合格を掴むための学習テクニック大全
▶テキストを購入するタイミング:FPテキストを買い替える基準は「法令基準日」!知らないと危険な法改正のポイント
まとめ|FP資格で得た知識を活用し、投資リスクとうまく付き合おう
投資は未来に備えるための手段ですが、知識という武器なくして戦うのはおすすめできません。
FPの学習を通じて得られる体系的な知識は、投資におけるリスクを適切に管理し、感情的な判断を避けるために必要です。
また、NISAやiDeCoなどのお得な制度の情報も得られるため、自身にとってプラスに働くでしょう。
FPの学習で身につくライフプランニングの視点は、自分だけの「投資軸」を確立する上で不可欠です。
経済的自由への道のりは簡単ではありませんが、正しい知識は道のりを照らす光となります。
自分の意思で本当にしたいことを選べる経済的自由への第一歩として、FP資格の学習からはじめてみてはいかがでしょうか。