
24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
60代からの仕事を考えたときに「体力的に無理なく、これまでの経験を活かせる仕事がしたい」と感じる人は多いのではないでしょうか。
変化の多い現代では、60代からの働き方は多様化しており、これまでよりも選択肢が多くなりました。
60代からの仕事でおすすめしたいのが、FP(ファイナンシャルプランナー)です。
FPの仕事は、希望する働き方を実現させやすいため、体力に自信がない人でも安心して働けるでしょう。
本記事では、60代からの仕事にFPが最適な理由から、FP試験対策のポイントまで詳しく解説します。
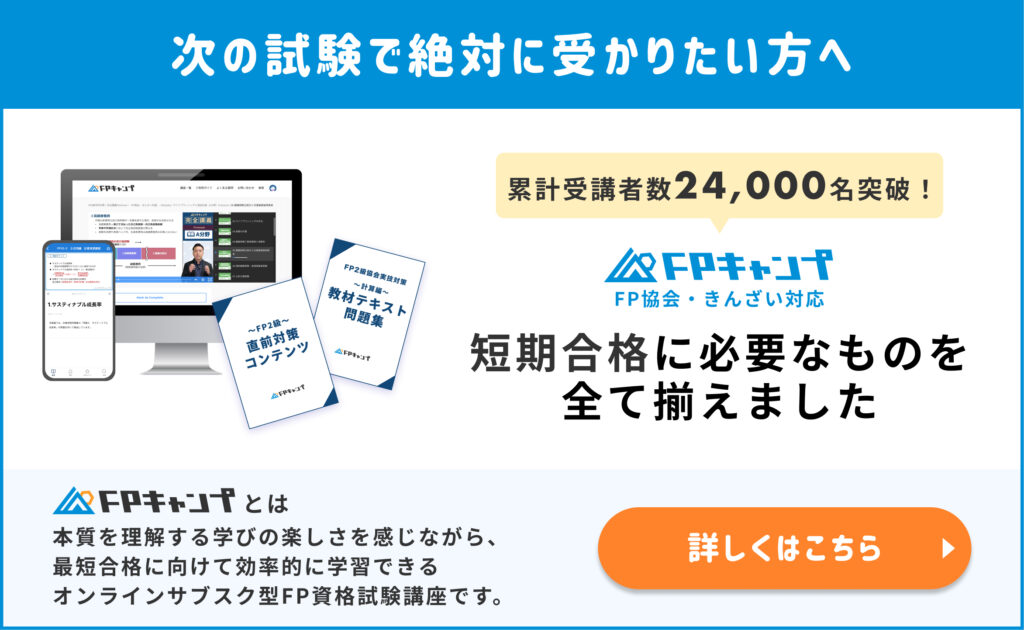
60代の働き方のリアルとは?働く理由と収入の目安
60代の就業率と収入を知り、セカンドライフをより充実したものに変化させる計画を練りましょう。
60代以上でも働く理由
働く理由には、「収入がほしいから」が最も多い反面、「老化防止・健康のため」「仕事が面白いから」などが挙げられました。
内閣府が行った「高齢者の経済生活に関する調査(2024年度)」の結果は、以下の通りです。
| 理由 | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 収入のため | 55.1% | 59.6% | 48.9% |
| 知識・能力を活かせるため | 12.4% | 13.1% | 11.5% |
| 老化防止・健康のため | 20.1% | 18.7% | 22.1% |
| 仕事が面白いため | 4.8% | 3.7% | 6.3% |
| 友人・仲間を得られるため | 3.0% | 1.7% | 4.8% |
| 不明・無回答 | 4.6% | 3.2% | 6.5% |
これらの結果から、収入を得るためだけでなく、健康面や社会とのつながりを意識する人も多い傾向にあります。
定年退職後の人生をさらに楽しむための方法の1つとして、60代でも働き続ける人が多いと考えられるでしょう。
最新の就業率は74.3%
総務省が行った「労働力調査(基本集計)」の2024年度版によると、60歳~64歳の就業率は74.3%でした。
以下の表では、2014年と2024年の就業率を紹介します。
| 対象年齢 | 2014年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 60~64歳 | 60.7% | 74.3% |
| 65~69歳 | 40.1% | 53.6% |
| 70~74歳 | 24.0% | 35.1% |
| 75歳 | 8.1% | 12.0% |
この結果からも、これまでの「定年後は働かない」という考え方が、大きく変化していることが分かります。
平均月収は、60歳~64歳約32万円、65歳~69歳で約28万円
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(2024年)」によると、平均月収は以下の通りです。
| 男性・女性 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 60歳~64歳 | 31万7,700円 | 34万4,700円 | 25万9,900円 |
| 65歳~69歳 | 27万5,500円 | 29万4,300円 | 23万4,000円 |
雇用形態や職種によって給与は異なるため、1つの目安として参考にしてみてください。
60代からの仕事にFPがおすすめな3つ理由
60代からの仕事に、FPがおすすめな理由を、3つの観点から解説します。
①体力に合わせて、柔軟な働き方ができる
FPは、60代からの仕事探しで押さえたいポイントでもある「体力的な負担」を考慮した働き方が可能です。
FPの業務は、基本的にデスクワークや対面でのコンサルティングが中心で、肉体的な負担が少ない特徴があります。
立ち仕事や重い物を持つ作業ではないため、体力に自信がない人でも安心して長く続けられるでしょう。
完全在宅ができる仕事を選べば、通勤の負担もなく、通勤時間をリラックスタイムに変えられます。
また、フリーランスとして働く場合は、仕事量も調整できるので、精神的な負担も軽減可能です。
「来週は旅行に行くから、今週は大目に働く」など、ライフスタイルに合わせた働き方ができる点は、FPならではのメリットです。
FPは、体力やプライベートの予定に合わせて働き方をデザインできるため、60代からの仕事に最適だといえます。
企業に所属する「企業系FP」、独立開業して働く「独立系FP」、本業と掛け持ちして働く「副業FP」の詳細は、以下の記事をご覧ください。
▶関連記事:ファイナンシャルプランナーの働き方は柔軟!企業系・独立系・副業について解説
②人生経験そのものが「強み」になる
多くの仕事では、年齢がハンデになるケースも少なくありません。
しかし、FPは、豊かな人生経験こそが他の世代にはない「強み」として役立ちます。
例えば、30代夫婦が住宅ローンの相談にきた場合、住宅ローンの重圧や不安などを感じている人が多いでしょう。
そのため、住宅ローンを組んだ経験がない若いFPよりも、住宅ローンを返し切った60代FPに相談したいと考える人もいます。
お金の問題は非常にデリケートな内容になるため、知識だけでなく、顧客の悩みに寄り添えるだけの実体験も重要です。
子どもの教育資金・親の介護・相続対策など、これまで乗り越えてきた経験すべてが、顧客への説得力あるアドバイスにつながります。
年齢を重ねるほどキャリアアップにつながるFPは、60代におすすめしたい仕事といえるでしょう。
③自分と家族の資産を守り増やす力が身につく
FPの学習では、人生で知っておきたいお金の知識を勉強するため、自分と家族の資産を守り増やす力を身につけられます。
年金・保険・税金・資産運用など、60代の生活に関わるテーマが含まれており、これからの人生で役立つ重要な知識です。
例えば、退職金の運用方法を考えたり、相続で家族がもめないための準備をしたりなど、さまざまなシーンで活躍するでしょう。
娘家族の保険や孫の教育資金準備の相談にも乗れ、家族ためのマネードクターとしても活躍できます。
FPは、仕事としての収入だけでなく、自身の家計改善や資産形成という形でも大きなリターンをもたらす仕事です。
FP資格は必須?仕事内容は?
FPとして活動していく上で、知っておくべき重要なポイントを解説します。
FP2級以上がおすすめ!専門性の高さを証明しよう
資格がなくてもFPとして活動はできますが、専門性を証明できる資格を取得する方が、顧客から信頼を得られます。
実務レベルの知識をアピールできるのは、FP2級(2級FP技能士)以上になるため、働き方関係なく目指すとよいでしょう。
FP技能士は国家資格で、2級は金融や不動産に関する専門知識を持つ人材として客観的に評価されます。
履歴書や名刺にも記載できるので、セカンドキャリアのスタートを後押ししてくれる資格です。
顧客に安心感を与え、自身の専門性を証明するためにも、FP2級の取得を目標に設定し、計画的に学習しましょう。
仕事内容は幅広い!自身に合う内容を選ぼう
FPの仕事内容は幅広く、自身の得意分野や興味に合わせて活動内容を選べるのも大きな魅力です。
いくつかの仕事内容を紹介するので、チャレンジしたい内容を見つけてみてください。
- 個人相談(対面/オンライン)
例:保険の見直し・住宅ローンの選定・老後資金のプランニングなど
- セミナー講師(対面/オンライン)
例:新NISAの活用方法・iDeCoのはじめ方・円満な相続準備など
- 執筆、監修
例:Webサイト・電子書籍・書籍など
- SNS発信
例:X(旧Twitter)・Instagram・YouTubeなど
- アフィリエイト
例:クレジットカード紹介・医療保険紹介・証券口座紹介など
企業で働く場合は、個人相談業務・アシスタント・事務などを担当するケースが多いでしょう。
また、独立開業(事務所設立・フリーランス)や副業FPは、個人相談やセミナー講師、アフィリエイトなどから希望に合わせられます。
【おすすめの記事】
60代未経験でもファイナンシャルプランナーになれる?仕事内容・メリットなどを解説
【勉強が不安な人向け】60代からのFP試験対策ポイント
「今から勉強して試験に合格できるか不安…」と感じる人の不安を解消する、2つのポイントを紹介します。
久しぶりの勉強は、スキマ時間で無理なく継続
長年勉強から離れていると、記憶力や集中力に自信が持てない人も少なくありません。
60代からの資格学習で大切なのは、気力や体力まかせで頑張るのではなく、学習を日常に溶け込ませる工夫です。
「勉強を2時間しよう!」と高いモチベーションがあっても、慣れない作業に疲れてしまい、続かない人も多いでしょう。
しかし、5分~10分程度のスキマ時間で勉強すれば、無理なく1日1時間~2時間程度の学習時間を確保できます。
例えば、以下のように勉強を進めるのがおすすめです。
- 調理中に講義動画を視聴する
- ウォーキング中に苦手分野の講義を聞き流す
- 病院の待ち時間に単語帳を解く
- 銀行の待ち時間にアプリで問題を解く
短い時間でも、意識的に学習を繰り返せば記憶に残りやすくなり、精神的負担も軽くなります。
ただし、すぐに勉強をはじめられる環境作りが重要になるので、単語帳やアプリなどを活用するとよいでしょう。
「どの勉強をしよう?」と悩んでしまう人は、取り組む内容をあらかじめ決めておくのもおすすめです。
「丸暗記」より「なぜ?」を理解する
FP試験の範囲は6分野と広く、やみくもに暗記しようとすると、膨大な暗記量で挫折するケースも珍しくありません。
そのため、「なぜそうなるのか」という制度の背景や仕組みを理解し、本当に使える知識として定着させましょう。
深い部分まで理解できれば忘れにくく、応用問題にも対応できるようになります。
また、各分野の関連性を意識するのもポイントです。
例えば、住宅ローンには、住宅ローン控除・固定資産税(税金)や、住宅購入のための資産計画(ライフプランニング)などが絡んでいます。
各分野とのつながりが分かれば、実技試験で複雑な問題が出てきても、焦らず計算できるでしょう。
丸暗記に頼らず、深く理解する学習こそが、結果的に最短合格へとつながります。
勉強が苦手でも安心!FPキャンプが60代の学習をサポート
「独学は自信がない…」と不安に感じる人は、YouTubeで人気のFP解説者ほんださんが運営する「FPキャンプ」が最適です。
暗記量減!本質から学べるオリジナル学習
FPキャンプでは、先ほど紹介した「なぜ?」に先回りしながら、分かりやすさとユーモアを交えた講義を提供します。
各制度の本質から理解を深められるので、思考力で答えを導き出せるスキルを得られるでしょう。
暗記に頼る学習方法では、FPとして活動するときに活かしにくいデメリットがあります。
しかし、本質から理解できていれば、実務で使える「本当の知識」に変わり、よいスタートダッシュが可能です。
結果として、暗記量を大幅に減らせるため、勉強が苦手な人や久しぶりに学習する人でも、挫折することなく楽しく続けられるでしょう。
【おすすめの記事】
FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査
FP2級の合格率は全体平均超!質の高い講義が効果的
FPキャンプの質の高さは、合格実績にも表れており、FPキャンプ生のFP2級試験の合格率は、全国平均を上回る高い水準を誇ります。
全国平均とFPキャンプ生の合格率を、以下の表で比較しました。
FPキャンプ 2025年1月試験実績データ
| 対象試験 | 全体平均 | FPキャンプ生 |
|---|---|---|
| 学科試験 日本FP協会・きんざい | 31.6% | 87.8% |
| 実技試験 日本FP協会 (資産設計提案業務) | 48.8% | 92.6% |
| 実技試験 きんざい (個人資産相談業務) | 45.1% | 89% |
| 実技試験 きんざい (生保顧客資産相談業務) | 43.1% | 100% |
この結果は、FP解説で人気を誇るほんださんの講義が、いかに分かりやすく、効果的であるかを表しています。
スマホやパソコンでいつでもどこでも勉強できるため、通勤中や家事の合間といったスキマ時間で効率的に学習を進められます。
「60代からでも、FP試験に合格できるかな…」と不安を感じる人にこそ、FPキャンプの実績と質の高い学習環境は、心強い味方になるでしょう。

詳細は、FPキャンプの公式サイトをご覧ください!
まとめ|60代からの仕事は、FPの柔軟さと相性抜群
FPは、体力的な負担が少なく、ライフスタイルに合わせて柔軟な働き方ができる仕事です。
さらに、これまでの豊かな人生経験そのものが、顧客からの信頼を得るための武器として役立ちます。
FPの学習で得られる知識は、自分と家族の資産を守り、豊かにする一生モノの知識になるでしょう。
勉強に対して不安がある人は、合格実績が豊富な「FPキャンプ」を活用してみてください。
やりがい・収入・プライベートの充実を得られるFPを、60代からの仕事に選んでみてはいかがでしょうか。











