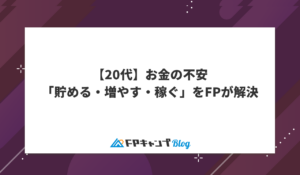24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
NISA・iDeCoなど、お金に関する言葉を聞く機会が増え、FP資格が気になる人も多いのではないでしょうか。
しかし、「FP3級は意味ないって聞くけど本当?」「FP3級だけでお金の勉強はできる?」と不安になる人も少なくありません。
本記事では、FP3級が「意味ない」といわれる理由から、取得するメリット・注意点などを徹底解説します。
FP3級がおすすめな人・不要な人の紹介もしているので、チャレンジするか悩んでいる人は判断材料にしてください。
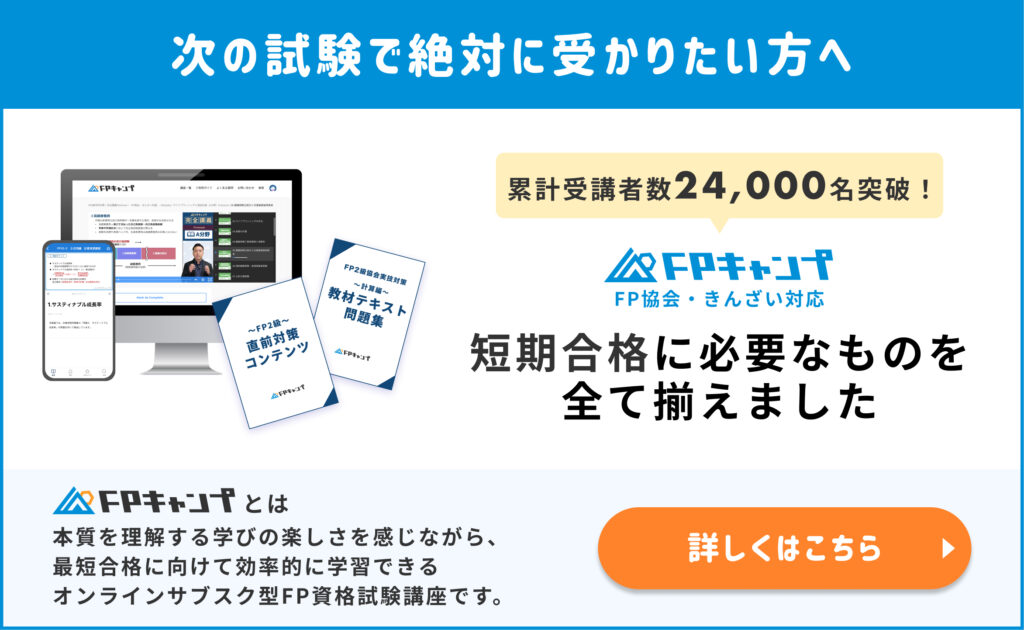
結論:FP3級は「意味ない」どころか、賢く生きるための知識
結論、FP3級は決して「意味がない」資格ではありません。反対に、現代社会を賢く生きる上で非常に役立つ、お金の基礎知識が詰まった資格といえます。
実際に、「FP3級だけでは就職に直結しない」「専門家としては物足りない」といった声があるのも事実です。
しかし、それらは一部のデメリットでしかなく、デメリットを上回るメリットがFP3級にはあります。
日常生活や自分の将来設計に活かせる知識が体系的に学べる点は、FP3級ならではの大きな価値です。
FP3級:意味がないといわれる理由とは?
FP3級が「意味がない」といわれる理由を、客観的に解説します。
専門性に欠ける
FP3級は、FPとして必要な6分野の入門的な知識を広く浅く学ぶため、特定の分野における深い専門知識までは習得できません。
【FP3級で学ぶ知識】
- A分野:ライフプランニングと資金計画
- B分野:リスク管理
- C分野:金融資産運用
- D分野:タックスプランニング
- E分野:不動産
- F分野:相続・事業承継
顧客により専門的なアドバイスをする場合、FP2級・1級、AFP・CFPといった資格で知識を深める必要があります。
この点から、FP3級の知識だけでは「専門家」と名乗るには不十分と感じられ、「意味がない」といわれる理由になっていると考えられます。
就職・転職・独立開業などで評価されにくい
前述通り、FP3級だけでは専門性が足りないため、就職・転職・独立開業をする際に評価対象にならないケースが多いです。
金融業界への就職・転職などで資格を活かしたい人は、FP2級以上を取得しましょう。
以上が、「意味がない」といわれる理由の1つだと考えられます。