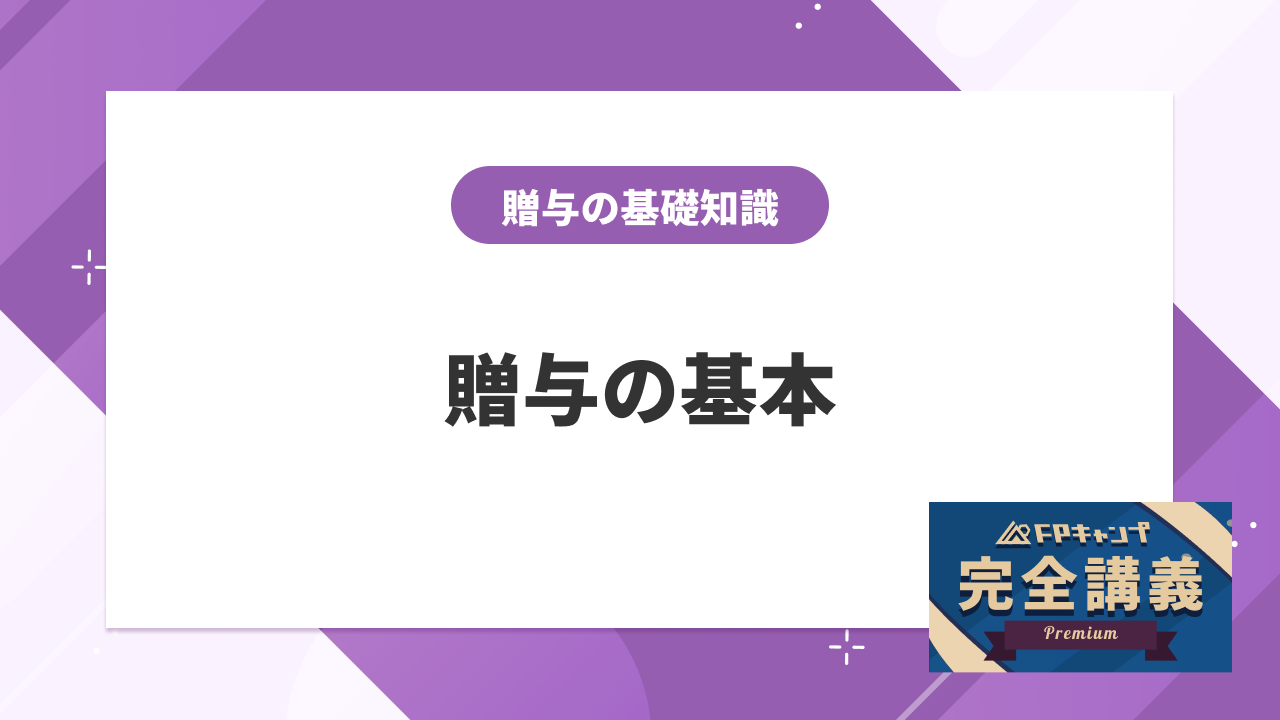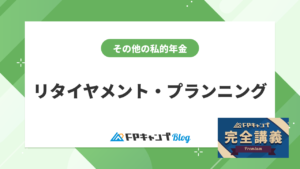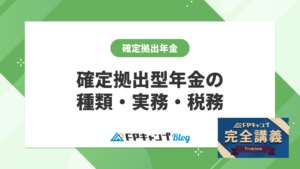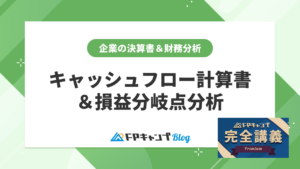24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
「贈与税」って聞くと、なんだか難しそう…自分には関係ないと思っていませんか?
実は贈与は私たちの生活に身近なもので、将来、相続や事業承継を考える上でもとても重要な知識なんです。
特にFP2級の試験では頻出テーマ!
でも、贈与の定義や成立要件、書面が必要なのかどうかなど、様々な疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
この記事では、贈与の基本的な知識を、FP2級受験者の方にも分かりやすく解説していきます。
贈与税の計算方法だけでなく、贈与の成立要件や名義預金の注意点など、実例を交えながら丁寧に説明しますので、ぜひ最後まで読んで、贈与の基礎をマスターしてくださいね!

贈与って、ただお金や物をあげるだけじゃないんですか?何か難しいルールがあるみたいで不安です…



そうですね、贈与にはいくつかルールがあります。でも、一つずつ丁寧に見ていけば大丈夫!一緒に勉強していきましょう。


贈与とは何か? FP2級対策にも必須の基礎知識
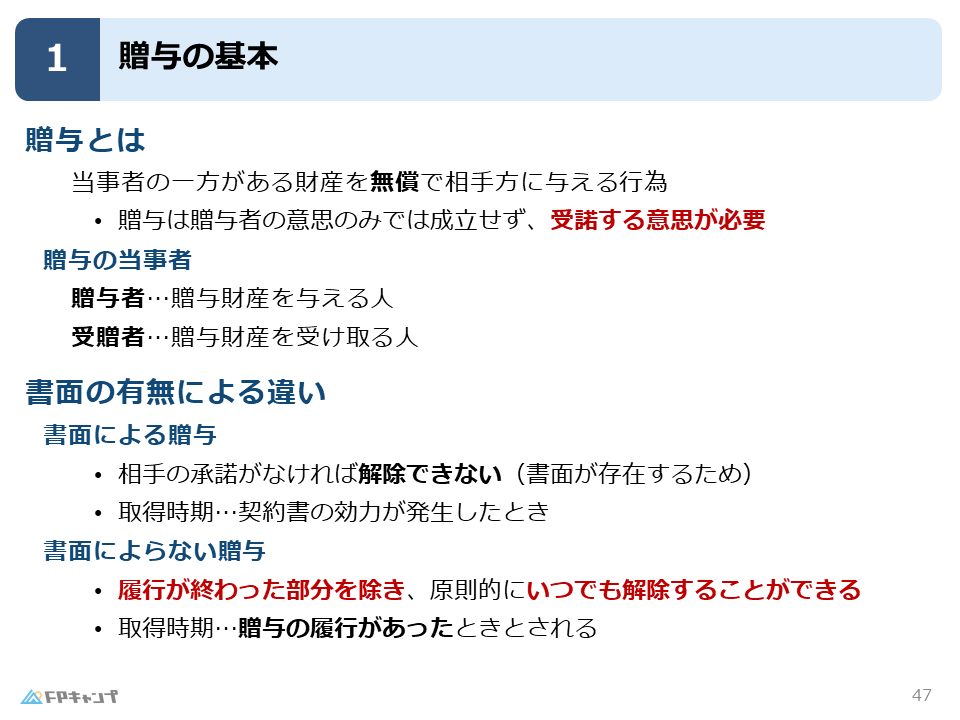
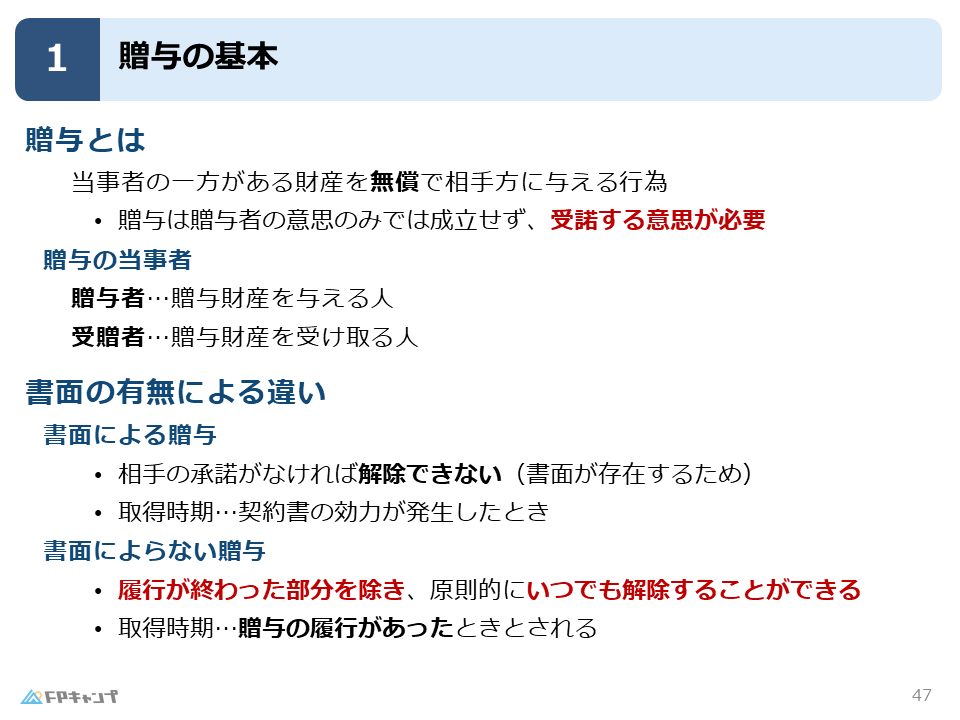
まず、贈与とは一体何なのでしょうか?
簡単に言うと「あげる」という意味ですが、FP2級の試験対策として、もう少し正確に理解しておきましょう。
贈与の定義をシンプルに解説
贈与とは、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える行為のことです。
つまり、お金や物などをタダで相手にあげることを言います。
無償であることの意味とは? 売買との違い
ここで重要なのは「無償」である点です。
もし、何かと交換で財産を渡すのであれば、それは売買契約になります。
贈与税を考える上で、贈与と売買の違いをしっかり理解しておくことが大切です。



なるほど。「無償」というのがポイントなんですね!



その通りです!贈与税を考える上で非常に重要なポイントです。しっかり覚えておきましょう。
贈与成立の要件:あげる側・もらう側の意思表示
贈与は、あげる側の意思表示だけでは成立しません。
もらう側の受諾する意思も必要です。
あげる側ともらう側、両方の意思表示が合致して初めて贈与が成立します。
贈与契約における「意思表示」の重要性
贈与は、贈与契約という契約の一種です。
契約は、当事者間の合意によって成立します。
つまり、贈与の場合、贈与者と受贈者の双方が贈与という行為について合意する必要があります。
この合意が「意思表示」です。
贈与者と受贈者:それぞれの役割
贈与を行う側を贈与者、贈与を受ける側を受贈者と言います。
贈与者は財産を与える人、受贈者は財産を受け取る人です。
両者の意思表示が合致することで、贈与契約が成立します。
「あげます」という贈与者の意思表示と、「もらいます」という受贈者の意思表示が必要です。



あげる側と、もらう側の両方の意思表示が必要なんですね。片方だけではダメっていうのは、なんとなくイメージが湧きます。



まさにその通りです。この点をしっかり理解しておくと、名義預金の問題など、後々出てくる論点の理解にも繋がりますよ。
名義預金にご用心! 贈与と認められないケース
相続対策として、早めに子供や孫にお金を移しておきたいという気持ちは分かります。
しかし、子供の銀行口座を作って勝手にお金を入れていくだけでは、贈与として認められない場合があります。
これは名義預金と呼ばれ、贈与税の落とし穴の一つです。
子どもの口座にお金を移すだけでは贈与にならない?
名義預金とは、名義上は子供の口座であっても、実際には親が管理し、子供に贈与する意思表示や、子供からの受諾の意思表示がない預金のことです。
税務署から贈与と認められないと、相続税の対象となってしまう可能性があります。
相続税対策で注意すべきポイント
相続税対策として、子や孫の口座に預金する場合、贈与契約が成立していることが重要です。単に預金するだけでなく、贈与契約書を作成する、または口頭で「贈与します」「贈与を受け取ります」という意思表示を明確にする必要があります。贈与契約が成立していないと、名義預金とみなされ、相続税の対象となる可能性があります。最悪の場合、多額の相続税を支払うことになりかねませんので、注意が必要です。



名義預金、気を付けないといけないですね…。贈与する時は、ちゃんと「あげます」「もらいます」を明確にしないとダメなんですね。



その通りです!贈与の意思表示は非常に重要です。曖昧なままにせず、しっかりと確認しておきましょう。
贈与契約の方式:書面あり? なし?
贈与契約は、必ずしも書面で作成する必要はありません。
口約束でも成立します。
しかし、書面がある場合とない場合では、それぞれメリット・デメリットがあります。
書面による贈与契約の特徴とメリット・デメリット
贈与契約書を作成する場合、贈与者と受贈者の双方が署名・捺印することで、贈与の事実を明確に残すことができます。
一度契約が成立すると、贈与者は簡単に贈与を解除することができません。
これは受贈者にとって大きなメリットです。
ただし、贈与契約書を作成するには、手間と費用がかかるというデメリットもあります。
書面によらない贈与契約の特徴とメリット・デメリット
書面によらない贈与契約は、口約束だけで成立するため、手軽で費用もかかりません。
しかし、贈与の事実を証明するのが難しく、トラブルに発展する可能性があります。
また、贈与者は贈与を解除しやすいため、受贈者にとってはリスクがあります。



書面を作るか作らないかで、こんなに違いがあるんですね!



はい、それぞれメリット・デメリットがあるので、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
贈与契約の解除:書面ありとなしの場合の違い
贈与契約は、一度成立すると、原則として解除できません。
しかし、書面がある場合とない場合では、解除の条件が異なります。
書面ありの場合の解除条件
書面による贈与契約は、受贈者の承諾がない限り、解除できません。
一度契約書にサインしてしまうと、後から「やっぱりやめる」とは言えないので、慎重に検討する必要があります。
書面なしの場合の解除条件:履行の有無が鍵
書面によらない贈与契約は、贈与の履行が完了する前であれば、いつでも解除できます。
例えば、口約束で「お金をあげる」と言った後で、考えが変わって「やっぱりやめる」と言うことは可能です。
ただし、すでに一部でもお金を渡している場合は、その部分については解除できません。



書面がない場合は、お金を渡す前なら解除できるんですね。でも、一部でも渡していたら、その部分は解除できないというのは、ちょっと複雑ですね…。



そうですね。贈与の解除については、書面の有無によって大きく変わるので、しっかりと覚えておきましょう。
贈与の履行時期と財産の取得時期
贈与の履行時期と財産の取得時期は、贈与税の計算上重要なポイントです。
書面ありとなしで、それぞれ確認しましょう。
書面ありの贈与:契約書の効力発生日
書面による贈与の場合、贈与の履行時期は契約書の効力発生日となります。
契約書に「○月○日に贈与する」と記載されていれば、その日が贈与の履行時期となり、受贈者はその日に財産を取得したものとみなされます。
書面なしの贈与:実際の贈与が行われた日
書面によらない贈与の場合、贈与の履行時期は、実際に贈与が行われた日です。
つまり、実際に財産が贈与者から受贈者に渡った日が、贈与の履行時期であり、財産の取得時期となります。



贈与の履行時期と財産の取得時期…少しややこしいですが、税金の計算に関係してくるので、重要ですね。



その通りです!しっかり押さえておきましょう!
贈与税がかかる贈与財産:お金だけじゃない!
贈与税は、贈与財産に対して課税されます。
贈与財産とは、贈与の対象となる財産のことですが、お金だけでなく、様々なものが含まれます。
具体的には、不動産、株式、貴金属、自動車など、金銭的価値のあるもの全てが贈与財産となり得ます。
FP2級の試験では、贈与税の対象となる財産の種類についても理解しておくことが大切です。
| 財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 金銭 | 現金、預貯金 |
| 不動産 | 土地、建物 |
| 有価証券 | 株式、債券 |
| 動産 | 自動車、貴金属、美術品 |
| その他 | ゴルフ会員権、特許権 |



お金以外も贈与税の対象になるんですね!



そうなんです。金銭的価値のあるもの全てが対象になり得るので、注意が必要ですよ。
まとめ:贈与の基本と注意点をおさらい(FP2級受験者向け解説付き)
この記事では、贈与の基本について解説しました。
贈与とは無償で財産を与える行為であり、贈与者と受贈者の意思表示が合致することで成立します。
名義預金は贈与と認められないケースがあるので注意が必要です。
贈与契約は書面がなくても成立しますが、書面の有無によって解除条件が異なります。
贈与税は、金銭だけでなく様々な財産が対象となります。
FP2級の試験では、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう。
贈与の成立要件と名義預金の落とし穴
贈与の成立には、贈与者と受贈者の双方の意思表示が必須です。
子供の口座にお金を移すだけでは贈与とは認められず、名義預金とみなされる可能性があります。
名義預金は相続税の対象となるため、注意が必要です。
書面あり・なしの贈与契約の違いを再確認
贈与契約は書面がなくても成立しますが、書面がある場合となしでは、解除条件が異なります。
書面がある場合は受贈者の承諾なしに解除できませんが、書面がない場合は贈与の履行前であれば解除できます。
状況に応じて適切な方法を選択しましょう。



贈与の基本、よく理解できました!FP2級の試験対策にも役立ちそうです!



素晴らしいですね!この調子で頑張ってください!応援しています!